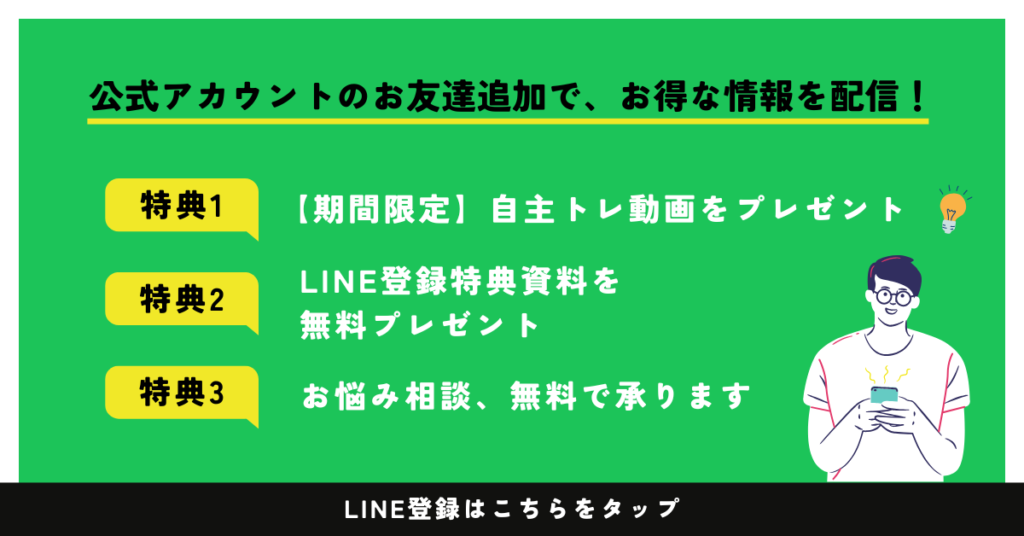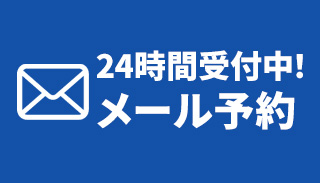脳梗塞後、足の指が曲がってしまうのは後遺症!?クロートゥって何?
ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)
脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。
「歩こうとすると、足の指がギュッと曲がってしまう…」 「立ち上がる時に、足の指が地面を掴むようにこわばる…」 脳梗塞や脳出血の後遺症でリハビリを頑張っている方から、このようなお悩みを非常によく伺います。
ご自身ではコントロールできずに足の指が曲がってしまうこの症状、通称**「クロートゥ(Claw toe)」**と呼ばれています。この症状は、歩きにくさやバランスの悪さに繋がり、転倒のリスクも高めてしまう厄介なものです。
そこで今回は、なぜクロートゥが起こるのか、そのメカニズムからご自宅でできるセルフケア、そして専門的な改善アプローチまで、リハビリの専門家として分かりやすく解説していきます。
トピック1:なぜ足の指が曲がる?クロートゥの原因
クロートゥは、専門的には「緊張性足趾屈曲反射(TTFR)」とも呼ばれます。これは、脳卒中などによって脳がダメージを受けたことで起こる「錐体路障害(すいたいろしょうがい)」という症状の一種です。
簡単に言うと、 『脳』からの「こう動いて」という運動指令が、『筋肉』にうまく伝わらなくなることで起こります。
特に、立ち上がりや歩行など、足への刺激や筋肉の緊張が高まりやすい動作で顕著に現れるのが特徴です。体が「頑張って動こう」とすればするほど、脳からの指令が複雑になり、処理が追いつかずに誤った指令(指を曲げろ!)が出てしまうのです。
トピック2:放置は危険!クロートゥが引き起こす二次障害
クロートゥは、バランスが悪くなるだけでなく、放置するとさらに別の問題を引き起こす可能性があります。
- 足趾の変形: 常に指が曲がった状態が続くと、関節が固まり、変形してしまうことがあります。
- 足趾の炎症や傷: 曲がった指が靴に当たったり、地面に擦れたりして、タコやマメ、ひどい場合は傷ができてしまうことがあります。
- 筋力低下: 正しく足の指を使えないため、足裏の筋肉が衰えてしまいます。
- 転倒リスクの増大: これらの要因が重なることで、バランス能力や歩行能力がさらに低下し、転倒の危険性が非常に高まります。転倒による骨折は、さらなる二次障害を招くことになりかねません。
トピック3:クロートゥへの専門的なアプローチ方法
クロートゥに対しては、様々な改善アプローチがあります。ここでは代表的なものを4つご紹介します。
-
①装具療法 あなたの足に合った装具(短下肢装具など)やサポーター(トゥスプレッドなど)を使用します。指先までしっかりサポートするものや、指の間にクッションを挟むことで、足裏の接地面積を増やし、過剰な緊張を抑えたり、痛みを和らげたりする効果が期待できます。
-
②ボツリヌス療法(ボトックス) 筋肉の緊張(痙縮)が非常に強い場合に有効な治療法です。「脳卒中治療ガイドライン2015」でも推奨されています。緊張している筋肉にボツリヌス菌の毒素を注射することで、筋肉の緊張を和らげます。この治療とリハビリを組み合わせることで、クロートゥの改善が期待できます。
-
③電気療法 麻痺した神経や筋肉に対し、電気刺激を与えて筋活動を促す方法です。クロートゥの原因となっている、ふくらはぎや足裏の筋肉に的確にアプローチし、リハビリと併用することで、過剰な緊張を抑える効果が期待できます。
-
④リハビリテーション クロートゥの改善には、専門家によるリハビリテーションが不可欠です。 私たち理学療法士や作業療法士が、あなたの体の状態に合わせて、適切な運動や動作の指導を行います。
トピック4:ひとりでできる!クロートゥ改善のためのセルフケア
専門的なリハビリと並行して、ご自身でできるケアに取り組むことも非常に重要です。 クロートゥは、脳が正しい情報をうまく処理できずに起こる症状です。そのため、以下の2つのポイントを意識することが、改善への近道となります。
- 『感覚』を意識すること
- 動作は『ゆっくり』行うこと
【立ち上がり直後から指が曲がる方へ:正しい立ち上がり方】 立ち上がる瞬間にクロートゥが起こる方は、立ち上がり動作そのものを見直す必要があります。
- 座位の確認: 椅子に座った時、左右のお尻に均等に体重が乗っているか、足の裏全体がしっかりと床についているかを感じてみましょう。
- お辞儀の確認: お辞儀をするようにゆっくりと体を前に倒します。お尻から太ももへ、そして足の裏へと体重がスムーズに移動していくのを感じてください。
- 伸び上がりの確認: 左右の足裏全体に体重が乗ったことを確認してから、ゆっくりと立ち上がります。
この3つのステップを「ゆっくり」「感覚を意識して」行うことで、脳への情報伝達がスムーズになり、クロートゥが起こりにくくなります。
【まとめ】 今回は、脳卒中後の後遺症である「クロートゥ」について、その原因から対処法までを解説しました。
クロートゥは、歩行やバランスに大きく影響するつらい症状ですが、原因を理解し、あなたに合ったリハビリや正しい体の使い方を身につけることで、変化を実感できることも少なくありません。
何よりもまず、ご自身の体の状態を専門的な視点で評価してもらうことが大切です。 もし、クロートゥやその他の麻痺症状でお困りでしたら、 ぜひ一度、私たちマヒリハにご相談ください。 あなたの「歩きたい」という想いを、専門家チームが全力でサポートいたします。
ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ
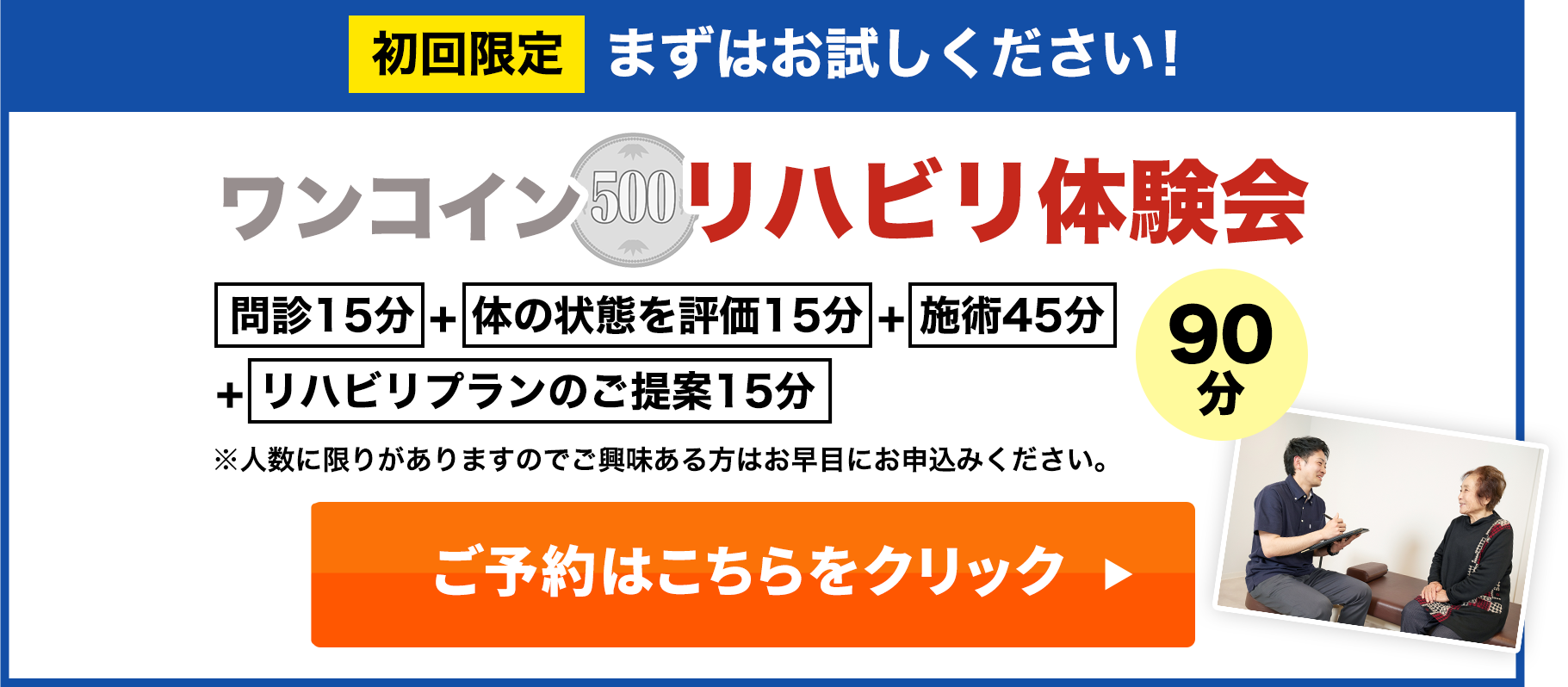
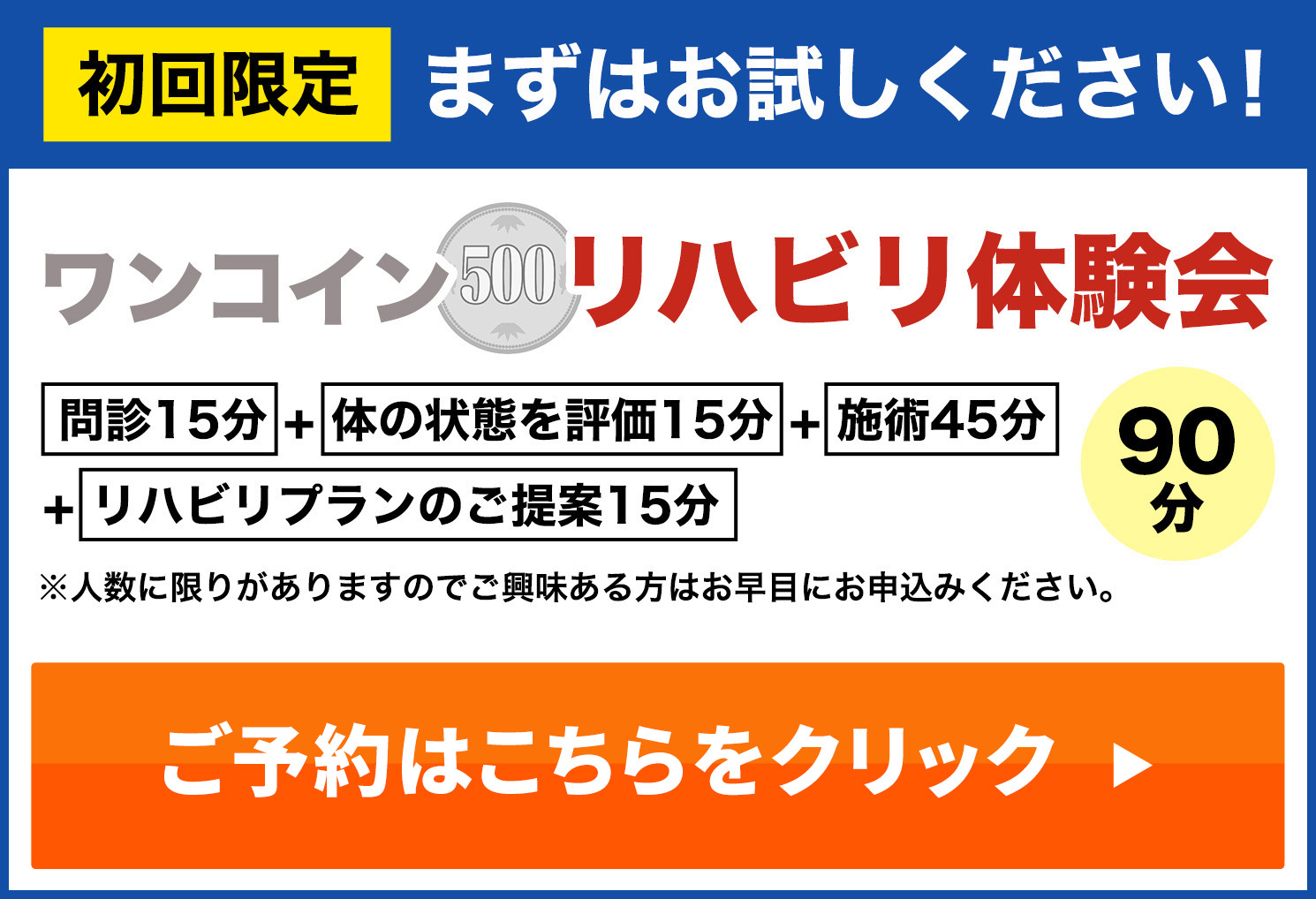
| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |
|---|---|
| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |
| 電話番号 | 04-7197-5090 |
| 定休日 | 日、金、祝 |