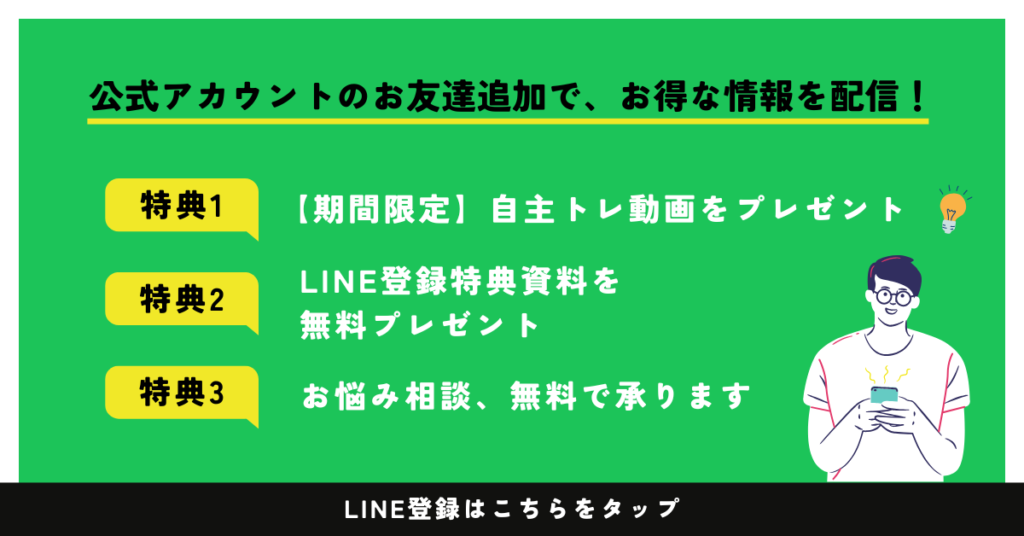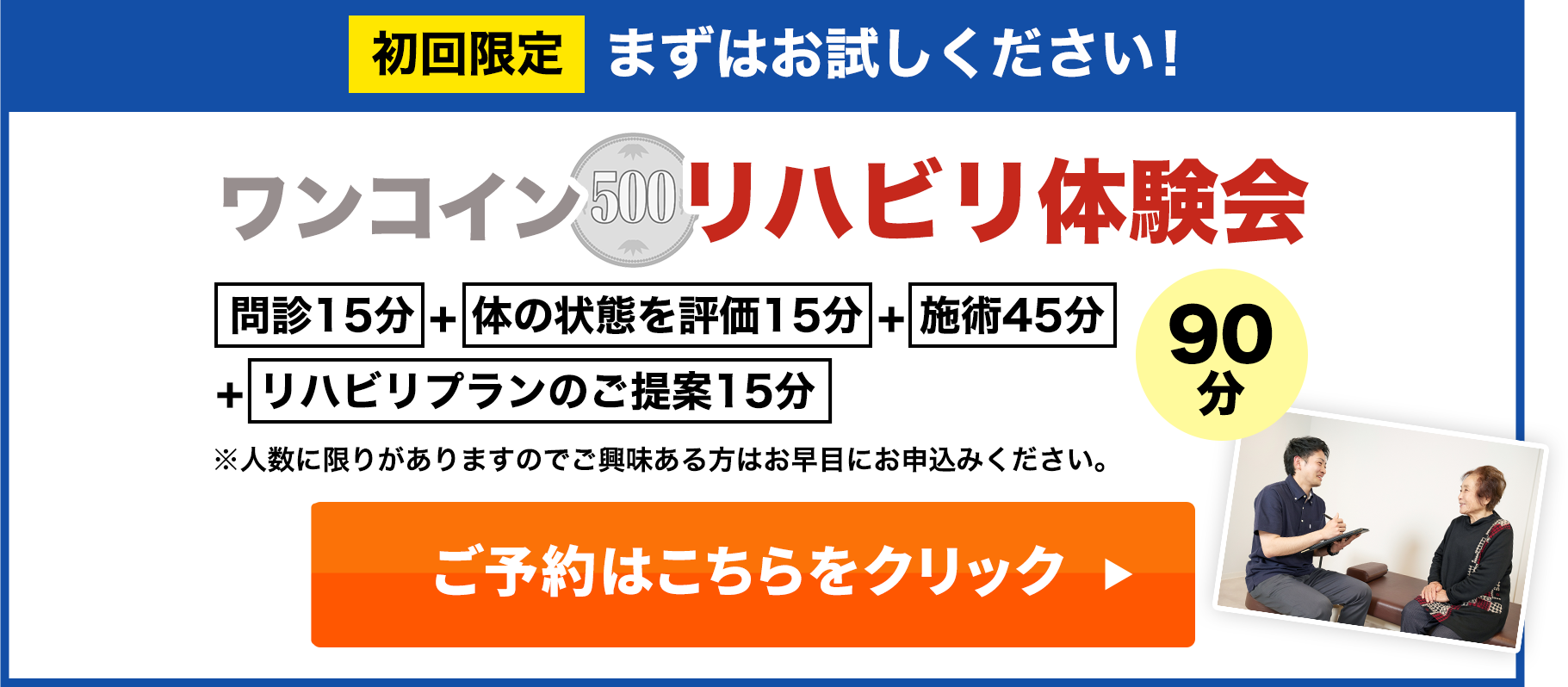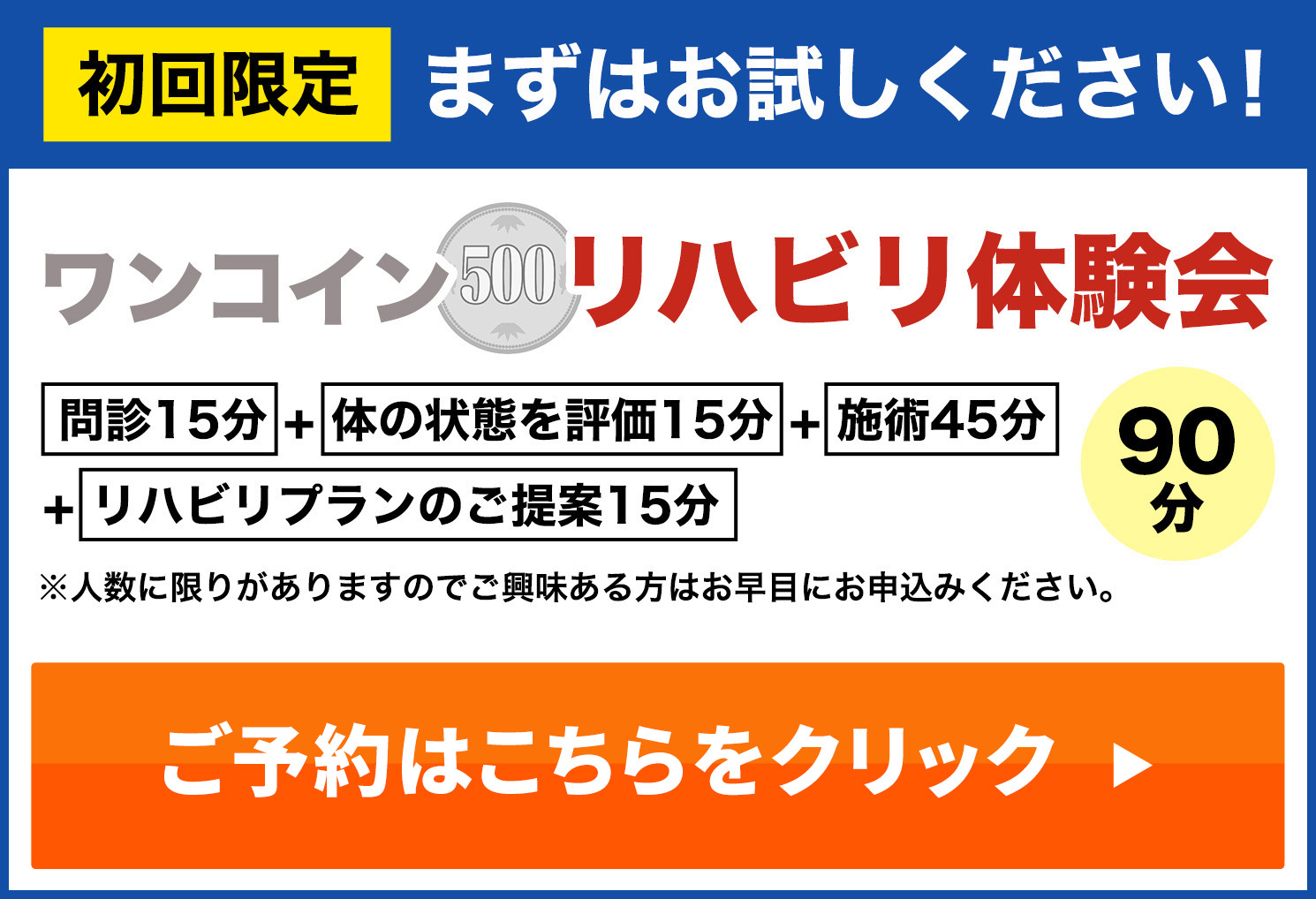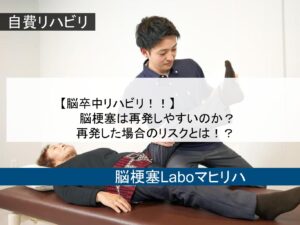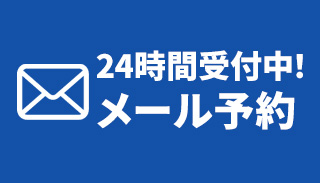こんにちは! 脳梗塞リハビリ専門施設「マヒリハ」の佐藤です🌞
「脳梗塞になってから、トイレが異常に近い…」 「夜中に何度もトイレに起きてしまい、ぐっすり眠れない」 「急に強い尿意が来て、間に合わないことがある」
加齢による変化としても現れますが、特に脳梗塞や脳出血を発症された後、このような「頻尿」や「尿意切迫感」に悩まされる方は非常に多くいらっしゃいます。 デリケートな問題のため、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方も少なくありません。
そこで今回は、リハビリの専門家として、
- なぜ脳梗塞後に頻尿が起こりやすくなるのか、そのメカニズム
- 尿意を我慢できなくなる「切迫性尿失禁」とは何か
- 病院での治療や、ご自身でできる対策
について、分かりやすく解説していきます。QOL(生活の質)に直結するこの問題を正しく理解し、改善への一歩を踏み出しましょう。

なぜ脳梗塞後に頻尿になるのか?脳と膀胱の連携トラブル
そもそも、私たちがおしっこをコントロールできるのは、脳と膀胱がうまく連携しているからです。 膀胱に尿がある程度たまると(通常300〜400ml)、その情報が脳に伝わり「トイレに行きたいな」と感じます。そして、脳が「よし、今だ」と指令を出すことで、膀胱が収縮し、尿道の筋肉が緩んで排尿が始まります。
つまり、脳は膀胱の暴走を抑える「ブレーキ」の役割を担っているのです。
ところが、脳梗塞や脳出血によって脳にダメージが及ぶと、このブレーキシステムにトラブルが生じます。
その結果、排尿をコントロールする神経の働きが過剰になり(排尿反射の亢進)、膀胱に少ししか尿がたまっていないのに、脳が「今すぐ出せ!」と強い指令を出してしまうのです。
これが、脳梗塞後に頻尿や強い尿意切迫感が起こる最大の原因です。
また、高血圧をお持ちの方は、夜間に腎臓への血流が増加する傾向があり、夜間の尿量が増えることも夜間頻尿の一因となります。
尿意を我慢できない「切迫性尿失禁」とは
この「急に我慢できないほどの強い尿意」に襲われ、トイレまで間に合わずに漏らしてしまう状態を**「切迫性尿失禁」**と呼びます。
脳卒中後の患者様に見られるのは、主に**「運動性切迫性尿失禁」**と呼ばれるタイプです。 これは、脳の排尿中枢の障害により、ご自身の意思とは関係なく、膀胱が勝手に異常収縮してしまう(無抑制収縮)ことで起こります。膀胱炎や前立腺肥大症などが原因で起こる「知覚性」とは区別されます。
頻尿・尿漏れに対して、自分でできること・相談できること
頻尿はQOLを著しく低下させますが、決して「歳のせい」「仕方がないこと」と諦める必要はありません。適切な治療や対策で改善が期待できます。
1. 専門医への相談と薬物療法
まずは泌尿器科などの専門医に相談することが基本です。治療の主体は、膀胱の異常な収縮を抑え、尿をためやすくするお薬(抗コリン薬やβ3作動薬など)による薬物療法となります。
2. 生活習慣の見直し
- 水分の摂り方: 水分を控えるのは脱水や脳梗塞再発のリスクを高めるためNGです。一度にがぶ飲みせず、こまめに飲むようにしましょう。また、利尿作用のあるカフェイン(コーヒー、緑茶)やアルコールは控えめに。特に就寝前の摂取には注意が必要です。
- 体を冷やさない: 体が冷えると尿意を感じやすくなります。服装や室温を調整し、体を温めましょう。
3. 骨盤底筋トレーニング
「骨盤底筋」は、尿道を締めて尿漏れを防ぐ“最後の砦”となる重要な筋肉です。この筋肉を鍛えることで、急な尿意が来た時に「キュッ」と我慢する力を高め、ちょい漏れを防ぐ効果が期待できます。
<簡単なトレーニング方法>
- 仰向けに寝て、両膝を軽く立てます。
- 肛門と尿道を締めるようなイメージで、ゆっくりと5秒間力を入れます。
- その後、ゆっくりと10秒かけて力を抜きます。
- この動作を10回ほど繰り返します。
4. トイレトレーニング(膀胱訓練)
少し尿意を感じてもすぐにトイレに行かず、「5分だけ我慢してみる」ことから始め、徐々にその時間を延ばしていく訓練です。膀胱に尿をためる感覚を再学習させ、排尿の間隔を広げていくことを目指します。ただし、専門家の指導のもとで行うことが推奨されます。
【まとめ】
脳梗塞・脳出血後の頻尿や尿漏れは、膀胱そのものではなく、脳のダメージによるコントロール機能の低下が主な原因です。 多くの人が悩む症状であり、決して恥ずかしいことではありません。
夜間の睡眠が妨げられたり、外出が怖くなったりと、生活の質に大きく関わるからこそ、一人で悩まずに、まずはかかりつけ医や泌尿器科の先生に相談してみてください。
適切な治療やセルフケアで症状が改善すれば、夜もぐっすり眠れ、安心して外出できるようになります。生活の質を取り戻すための大切な一歩を、ぜひ踏み出してみてください。