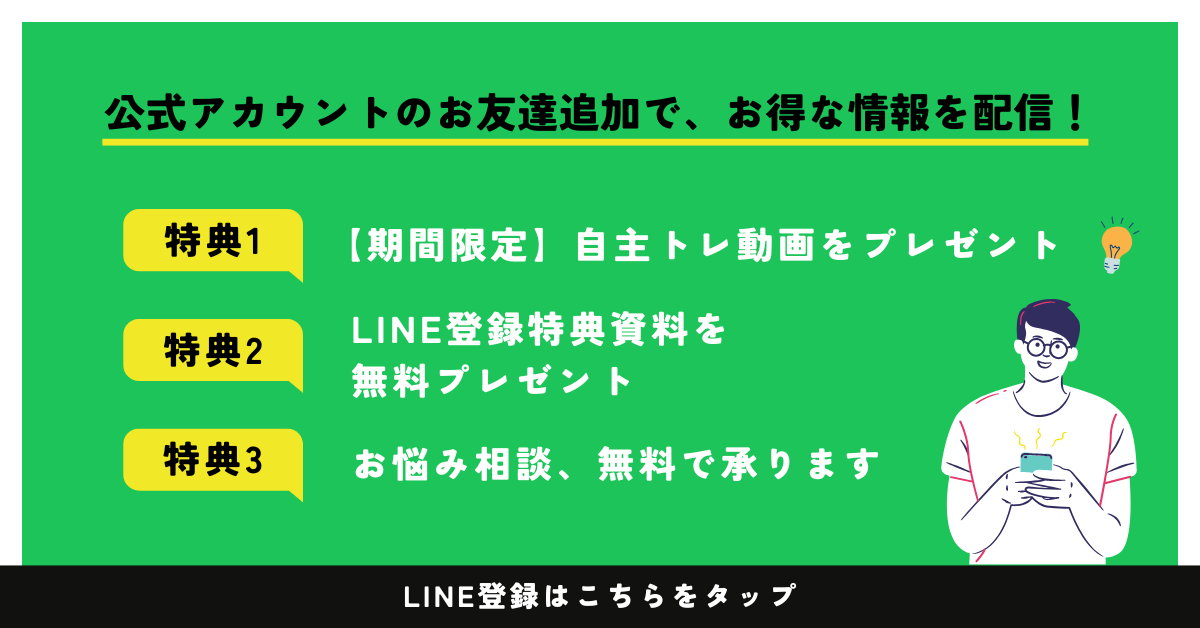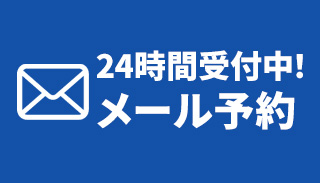【認定理学療法士監修】再発を防ぐ第一歩 脳梗塞・脳出血と向き合う“生活リハビリ”
ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)
脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。
【再発を防ぐ第一歩】脳梗塞・脳出血と向き合う“生活リハビリ”
こんにちは!マヒリハの原田です。
脳梗塞や脳出血を経験された方にとって、「もう二度と倒れたくない」という想いは共通の願いだと思います。
リハビリで少しずつ体を取り戻していく中で、実は何より大切なのが“日常生活の見直し”なんです。
今回は、「脳卒中の再発を防ぐ生活習慣」について、できること・気をつけたいことを一緒に整理していきましょう🍀
1. 食事は“血管にやさしく”
私たちの体は、食べたものでできています。
つまり、血管の健康=食事の質に大きく左右されるということ。
ポイントは、“バランス・減塩・水分”。
🥦 野菜と果物を意識的に
色とりどりの野菜や果物には、ビタミン・ミネラル・抗酸化物質が豊富。
食卓に「緑・赤・黄色」がそろうと、自然と栄養バランスが整ってきます。
🐟 タンパク質は“魚・豆・ナッツ”で
お肉だけでなく、青魚(サバ・イワシ)や豆製品も活用しましょう。
特に魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸は、血管をしなやかに保ってくれる頼もしい味方です。
🧂 塩分は控えめに
減塩を意識するだけで血圧コントロールがグッと楽になります。
出汁や香辛料を上手に使って、「味の満足感」はそのままに♪
🥤 水分を“こまめに”
水分不足は血液をドロドロにしてしまう大敵。
「のどが渇いた」ではなく、「意識して摂る」が大事なポイントです。
2. 運動は“毎日のくり返し”が力になる
「また倒れるのが怖くて…」と運動を控えていませんか?
じつは、適度な運動は再発を防ぐ最強の予防薬なんです💪
🚶♂️ 有酸素運動を取り入れる
ウォーキングや自転車こぎ、軽いジョギングなど、息が少し上がる程度の運動を毎日30分。
無理はせず、“毎日少しずつ”がコツです。
🧘♀️ 筋トレ&ストレッチも忘れずに
週2〜3回、軽い筋力トレーニングを加えると◎。
下半身の筋力アップは、転倒防止にもつながります。
3. タバコとストレス、どちらも“静かな敵”
🚭 禁煙は絶対条件!
タバコに含まれるニコチンやタールは、血管をボロボロにする猛毒。
再発リスクを下げたいなら、まずはここからスタートです。
☁️ ストレスに気づくこともリハビリの一部
ストレスを感じると、血圧が急上昇しやすくなります。
好きな音楽、入浴、軽い運動…あなたが“ホッとできる時間”を毎日の中に取り入れてください。
4. 小さな習慣が未来を守る
脳卒中を再発させないためには、“劇的な変化”よりも、地道な積み重ねが力を発揮します。
🧂 減塩
→ 塩分は1日6g未満を目標に
🧃 アルコール
→ 1日1合(ビールなら中瓶1本)程度にとどめる
💊 血圧・血糖・コレステロール管理
→ 医師の指示にしたがって、定期受診と内服を忘れずに
🌈 まとめ|「ふつうに暮らす」が最大の予防
脳梗塞や脳出血を経験された方にとって、**「再び倒れないこと」**が何よりも大事な目標です。
でもそれは、特別なことではありません。
・バランスの取れた食事
・少しの運動
・心の余白
・毎日の自己管理
この“ふつうの積み重ね”こそが、再発を遠ざけ、あなたの未来を守ります。
どうか一人で抱え込まず、わたしたち専門職にも気軽に相談してくださいね☺️
あなたらしい毎日を、ずっと続けていくために🍀
ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ
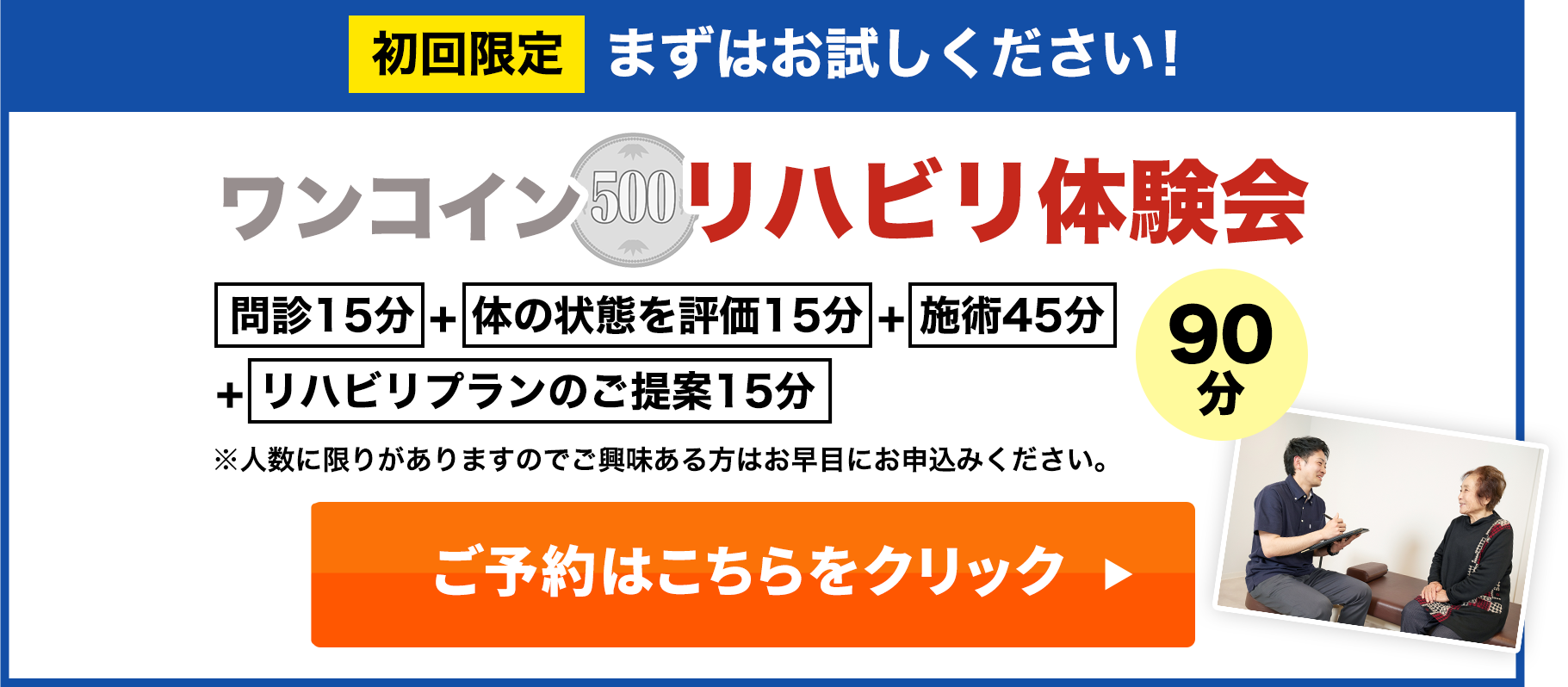
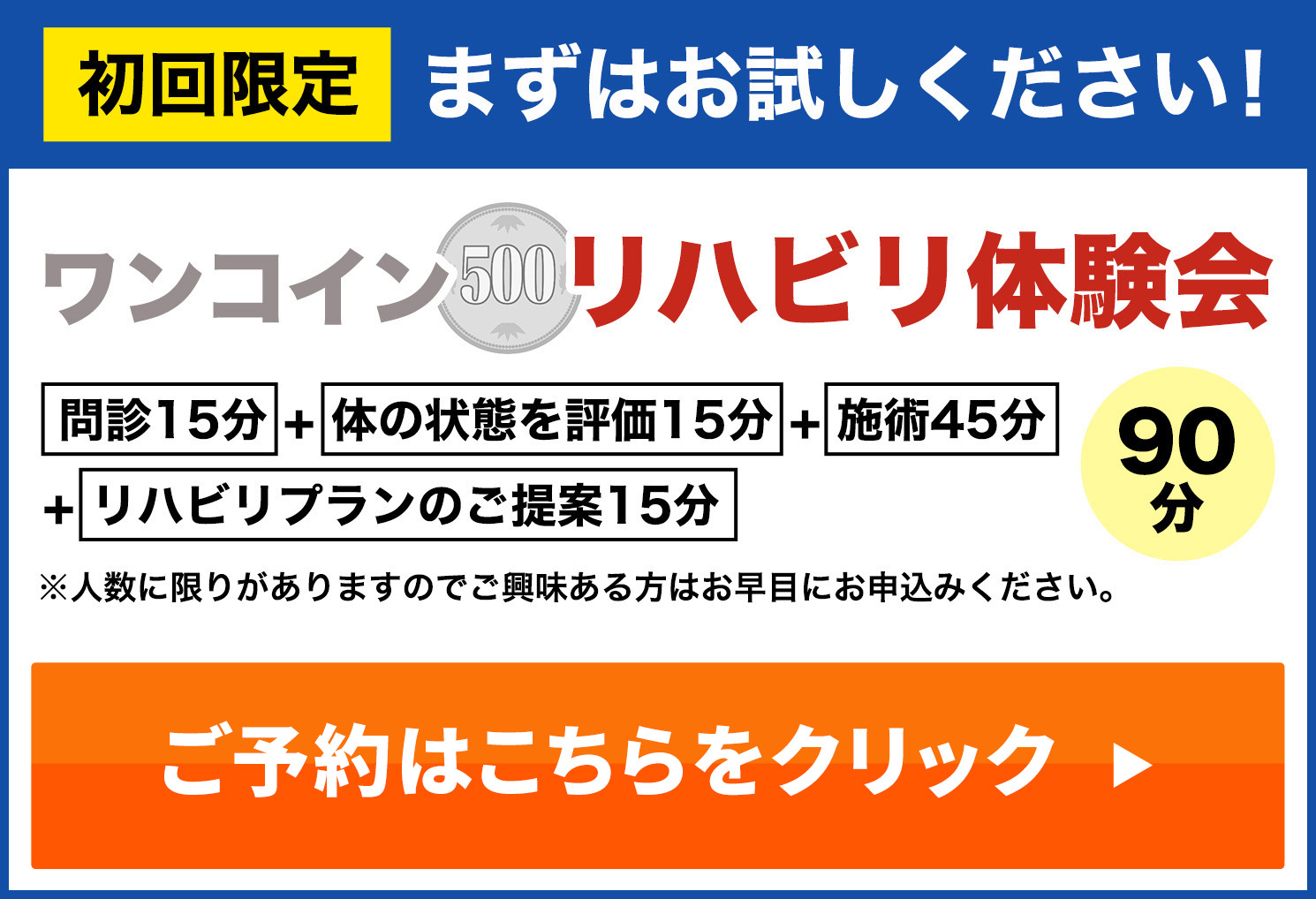
| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |
|---|---|
| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |
| 電話番号 | 04-7197-5090 |
| 定休日 | 日、金、祝 |