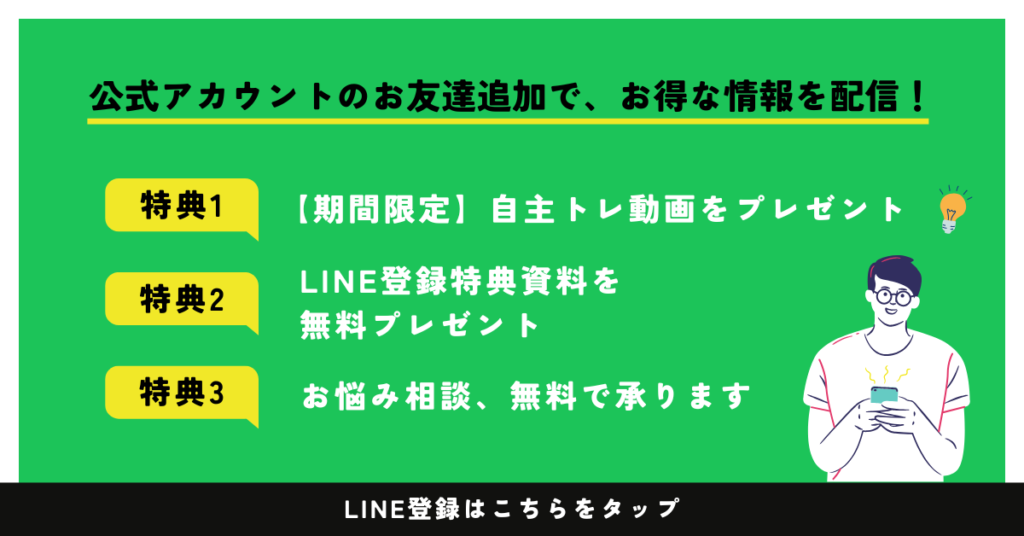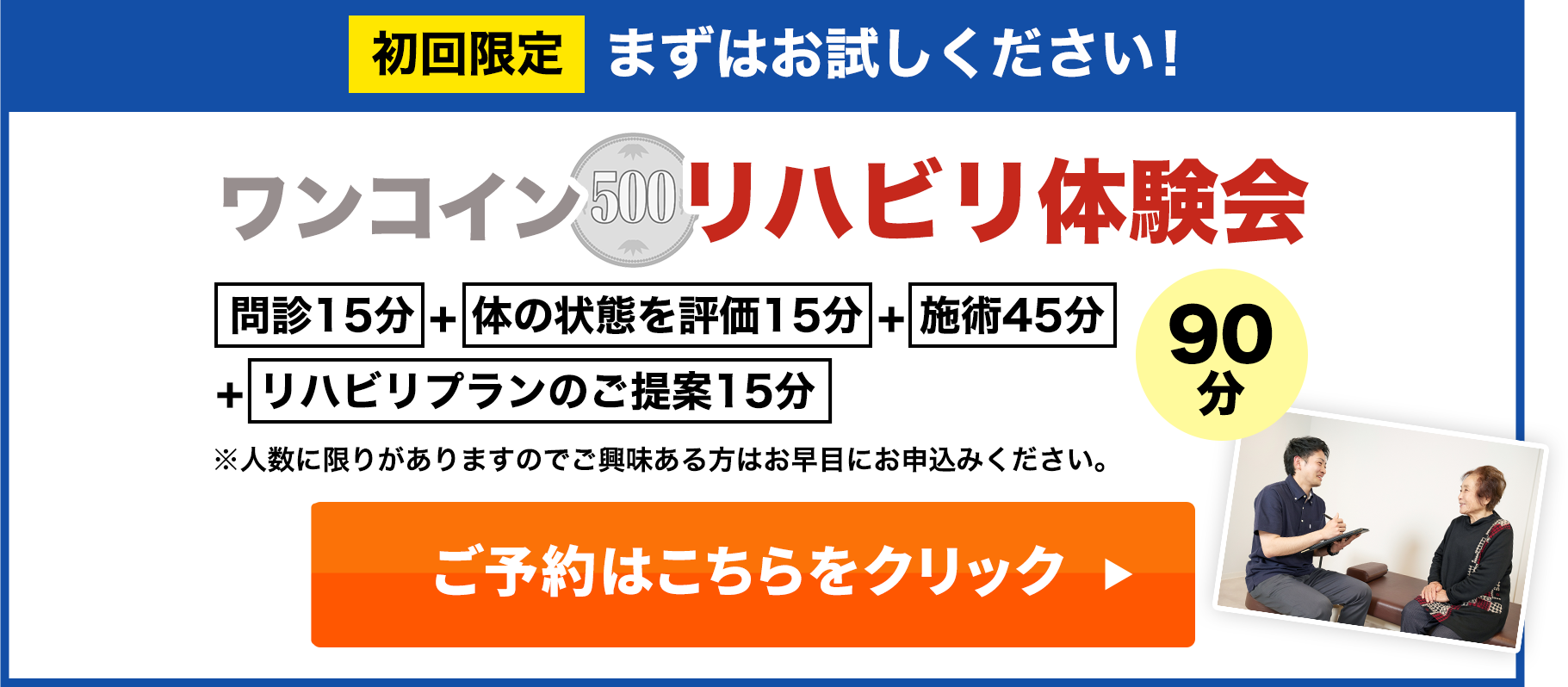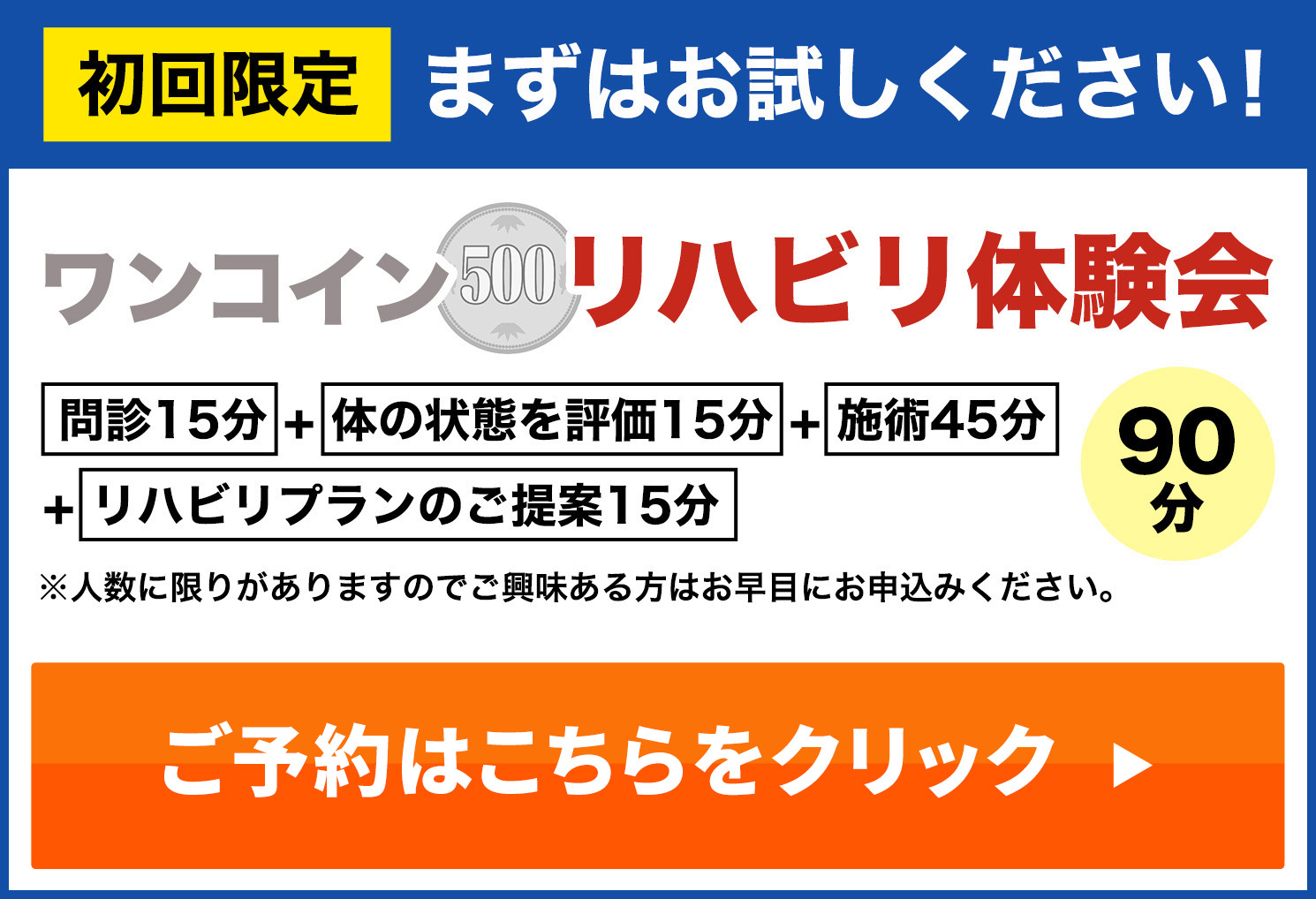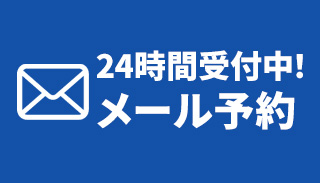🍽「食べること」が怖くなっていませんか?
〜脳卒中後の“むせ”と嚥下障害〜
こんにちは!マヒリハの岡田です🌞
- 「最近、食事中にむせるようになった」
- 「ご飯がうまく飲み込めなくて、口に残る」
- 「大好きだった食事が、苦痛になってきた…」
そんなお悩みをお持ちの方、もしかしたらそれは 「嚥下障害(えんげしょうがい)」 かもしれません。
嚥下障害は、脳卒中後に多くの方が経験する後遺症の一つ。
放っておくと 命に関わる「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」 に繋がることもあり、早期の気づきとケアがとても大切です。
今回は、脳卒中後に「なぜ飲み込みにくくなるのか」、そして「どうすれば再び安全に、美味しく食事を楽しめるのか」について、マヒリハならではの視点でお話しします。

🧠 なぜ“むせる”のか? 〜脳と飲み込みの関係〜
私たちは普段、「ごくっ」と自然に飲み込んでいますよね。
でも実はこの瞬間、舌・喉・食道など 20以上の筋肉と神経が、0.5秒以内に連携 しています。
つまり、「飲み込む」という動作は、身体の中でもトップクラスに精密な動き。
その司令塔が“脳”です。
脳卒中によって、飲み込みをコントロールする脳幹(延髄)や大脳の一部がダメージ を受けると、
タイミングがズレたり、筋肉がうまく動かなくなってしまう――
それが、嚥下障害の正体です。
🚨「誤嚥性肺炎」って何が危険なの?
食べ物や唾液が誤って気管(空気の通り道)に入ってしまうことを 「誤嚥」 と言います。
誤嚥によって口の中の細菌が肺に入り込むと、誤嚥性肺炎 が起こります。
この肺炎、実は非常に厄介。
厚生労働省の統計によると、高齢者肺炎の約6割が誤嚥性肺炎 と言われています。
しかも、軽い誤嚥は 「むせない誤嚥」=不顕性誤嚥 として気づかれないまま進行することも…。
気づかないうちに、体の中では炎症が起こっていることもあるのです。
🔍 家族でもできる!チェックポイント
「最近、なんだか食事の様子がおかしいな」と思ったら、次のサインを観察してみてください👇
-
食事中・食後によく咳き込む
-
声がガラガラ、湿った声になる
-
口の中に食べ物が残る
-
食事に時間がかかる
-
熱が続く(原因不明の発熱)
一つでも当てはまる場合は、早めに専門家(言語聴覚士など)に相談を!
早期に対応できれば、肺炎のリスクを大幅に減らすことができます。
💪 マヒリハでの嚥下リハビリ 〜“安全に食べる力”を取り戻す〜
マヒリハでは、理学療法士 × 栄養アプローチ のチームで、嚥下障害に対応しています。
🔸 間接訓練
食べ物を使わずに行う訓練です。
口・舌・喉の筋肉を鍛える体操や、呼吸法、咳のトレーニングなど。
🔸 食事形態の提案
誤嚥を防ぐための食事形態(きざみ食、ミキサー食、とろみ調整など)も、
その人の状態に合わせて丁寧に提案します。
🌿 マヒリハの強み:
「リハビリ × 栄養 × 自律神経」トリプルアプローチ
嚥下は“筋肉の動き”だけではなく、“体のコンディション”にも大きく左右されます。
マヒリハでは、腸内環境・自律神経・栄養バランス の改善にもアプローチ。
全国でも珍しい、エステプロ・ラボ製品 を導入し、
体の内側から「飲み込みやすい体」へと整えるサポートを行っています。
腸が整えば、自律神経も安定し、
それが嚥下機能の改善や全身の回復にもつながります。
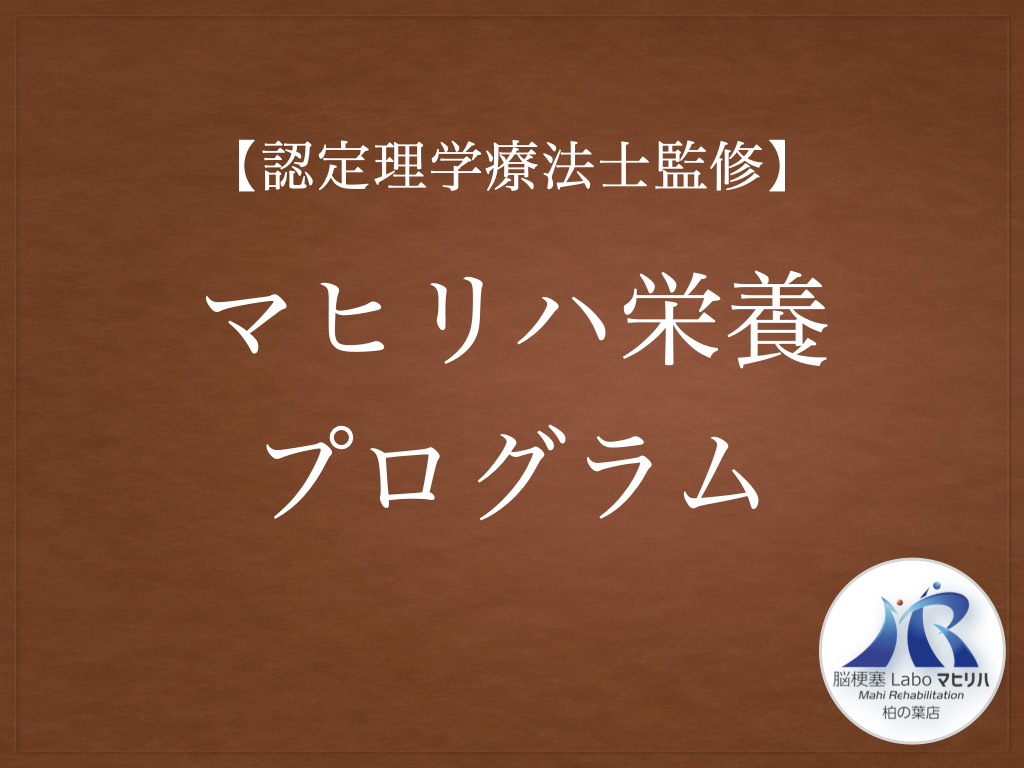
🍀 最後に:もう一度「食べる喜び」を取り戻そう
食事は、生きるための栄養補給だけではありません。
家族との団らん、季節の味覚、そして「おいしいね」と言える幸せ。
それが取り戻せたとき、リハビリの本当の意味が見えてきます。
もし今、
「むせて怖い」「食べるのがつらい」
そんな不安があるなら、どうか一人で悩まないでください。
私たちマヒリハが、あなたの“食べる力”と“生きる喜び” を全力で支えます。
🌞 ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。
マヒリハは、あなたの“再スタート”を全力で応援しています。