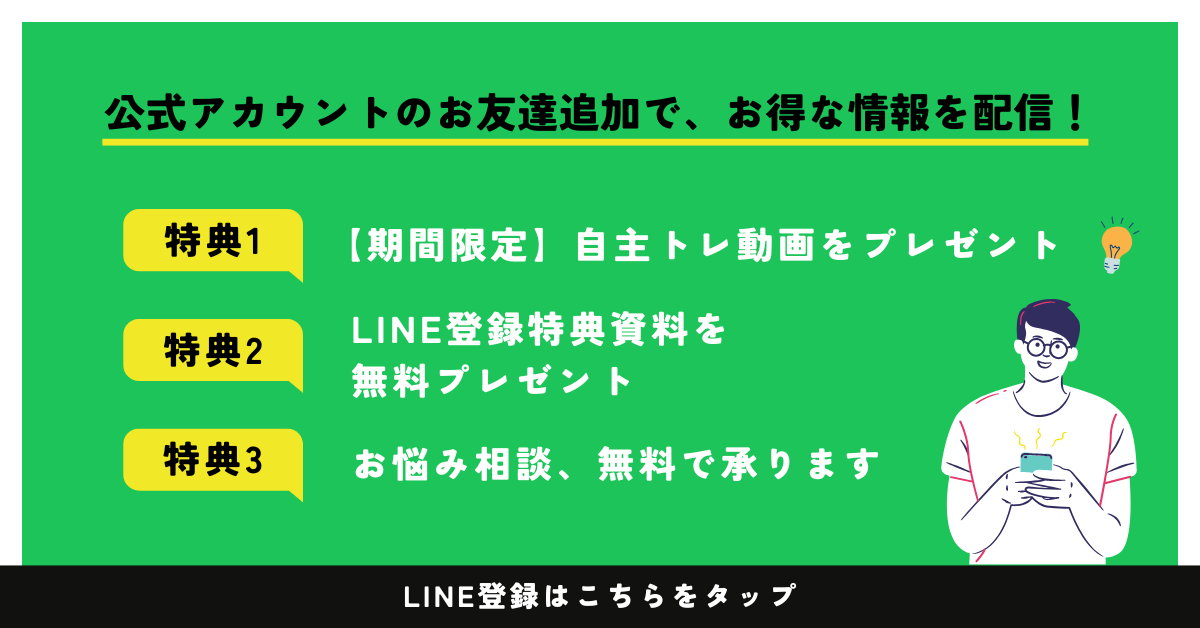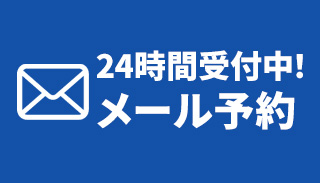【認定理学療法士監修】意識するだけで変わる。
ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)
脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。
🔎 意識するだけで変わる。
リハビリの「意識性の原則」—目的を持って動くと回復は加速する
こんにちは!マヒリハの原田です🌞
リハビリやトレーニングでよくいただく質問があります。「ただ動いてればいいんですか?それとも何かコツがあるんですか?」
答えはズバリ――「何のためにその運動をするのか」を明確にして、体のどこを使うかを意識すること。今回はその核心、マヒリハ流に深掘りします。
⚙️ 意識性の原則って何か?
トレーニングやリハビリで“目的意識”を持つこと。
目的が明確だと、つらい練習でも続けやすく、脳と体が効率よく“学習”します。
ただ漫然と動くのと、目的を持って同じ動作をするのでは、効果が全然違います。

🧭 具体例で理解しよう(現場でよくあるパターン)
目的:子どもを抱っこして自分で歩けるようにする
→ 必要な中間ゴール:立ち上がる・立位バランスを保つ・片脚支持ができる
→ 原因分析:立てない理由は“脚の筋力不足(特に大腿四頭筋)”と“立位バランスの低下”
→ 最初のトレーニング:ベッドサイドでの座位で大腿四頭筋を使う運動から開始
→ 意識ポイント:脚の前面(大腿四頭筋)を感じながら、膝を伸ばす。重りや抵抗は「使えている実感」を高めるための道具。
この一連の流れが「意識性の原則」の実践です。
🔍 なぜ“意識”が効くのか?(簡単なメカニズム)
-
脳へのフィードバックが強くなる
→ 「ここを動かす」と意識すると、その筋を支配する脳の領域がより活性化します。 -
不要な筋の代償が減る
→ 複数の筋を一緒に動かしてしまう癖(脳卒中でよくある)を抑え、目的の筋だけを使えるようになる。 -
学習の効率が上がる
→ 意識的な反復は神経回路の再編(可塑性)を促します。
🛠️ マヒリハ流:意識性を高める実践テクニック
-
鏡を使う:動きのフィードバックを視覚で確認する
-
声に出す:例えば「大腿四頭筋を使う!」と宣言してから動く(声の力で注意を集中)
-
指で触れる:鍛えたい筋を指で軽く押さえながら動く(触覚が注意を集める)
-
スローモーションで行う:速さを落とすと「どの筋が動いているか」が分かりやすい
-
イメージング:動作前に「この筋が縮む/伸びる」を頭の中で描く
-
ゴールを可視化:小さな目標(例:今週は立ち上がりを5回自力で)を設定して達成を積む

⚠️ 現場でよくある失敗パターン(注意点)
-
目的が曖昧なまま反復する → 効果が出にくくモチベ低下
-
「我慢すること」が目的になってしまう → 継続困難になる
-
多くの筋を同時に動かしてしまい、狙った筋に刺激が入らない
→ こうしたときは評価(理学療法士)で“どの筋が働いているか”をチェックしてもらいましょう。
✅ 日常に落とし込む短いルーティン例(ベッドサイド版)
-
座位で深呼吸(息を吐くときに骨盤を軽く引き上げるイメージ)
-
ゆっくり膝を伸ばす×10回(膝の前側を意識)
-
片脚で少し体重をかける練習(15秒×左右)
-
最後に「今日やったこと」を紙に一行メモ(達成感の積み重ね)
少しの“意識の工夫”で、毎日の積み重ねが変わります。
💡 脳卒中の方に特に伝えたいこと
脳卒中では「複数筋が一緒に動いてしまう」ことが多く、細かい筋の独立した動かし方を学び直す必要があります。だからこそ**“どの筋を使っているかを丁寧に感じる”**ことが重要です。時間はかかりますが、確実に体は応えてくれます。
📌 まとめ(マヒリハ流ポイント)
-
トレーニングは「目的」が9割。何のためにやるかを毎回確認しよう。
-
意識(視覚、触覚、言語化)が運動学習を加速する。
-
小さな目標と成功体験を積み重ねることが継続の鍵。
-
専門家の評価で「ちゃんと狙った筋が働いているか」を定期チェックすること。
ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ
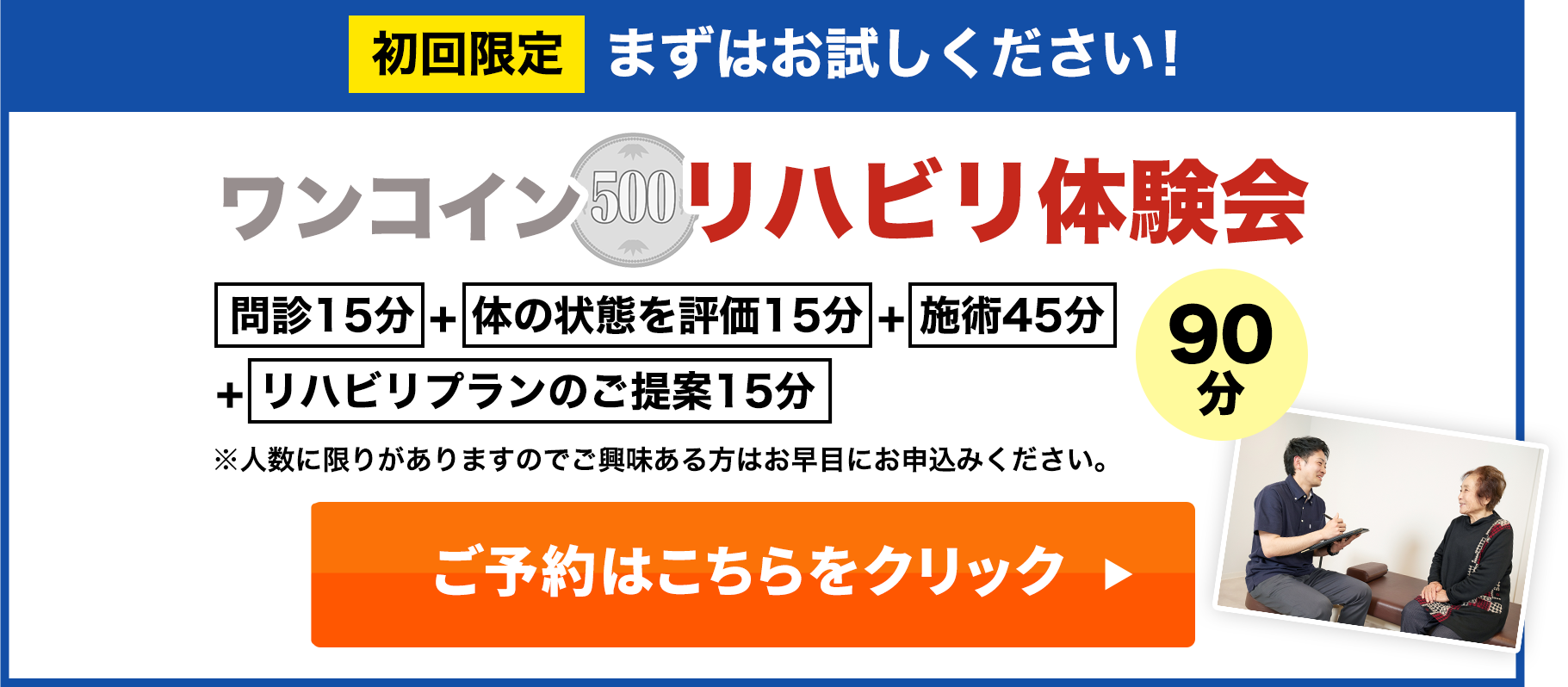
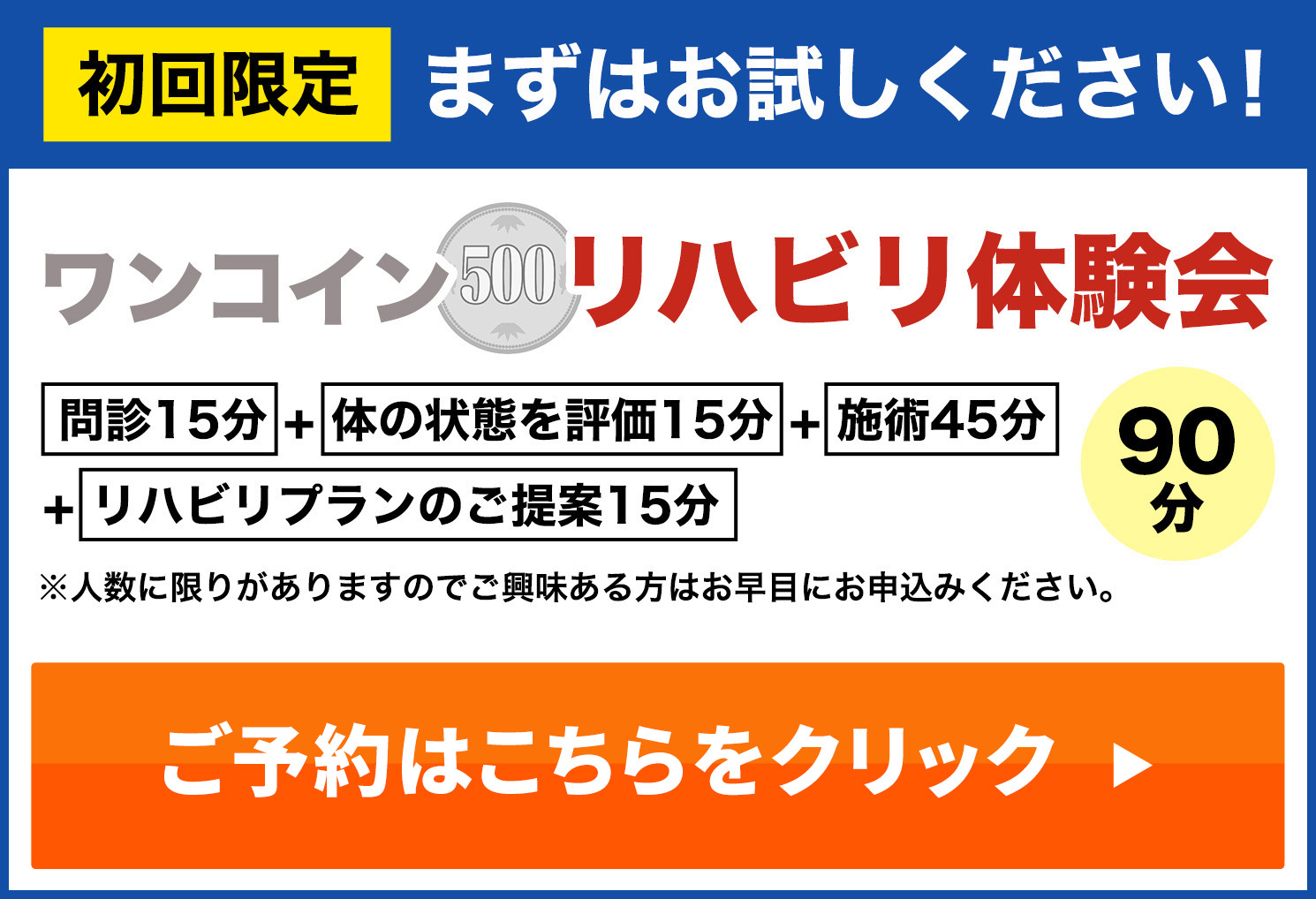
| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |
|---|---|
| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |
| 電話番号 | 04-7197-5090 |
| 定休日 | 日、金、祝 |