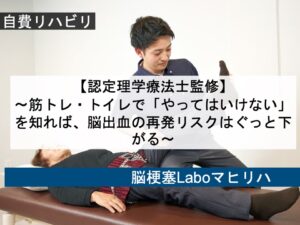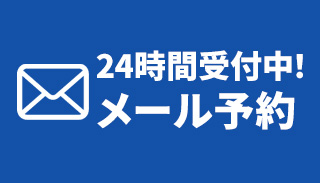【認定理学療法士監修】骨は折れないほうがいいに決まってる〜脳卒中後の“骨折リスク”〜
ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)
脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。
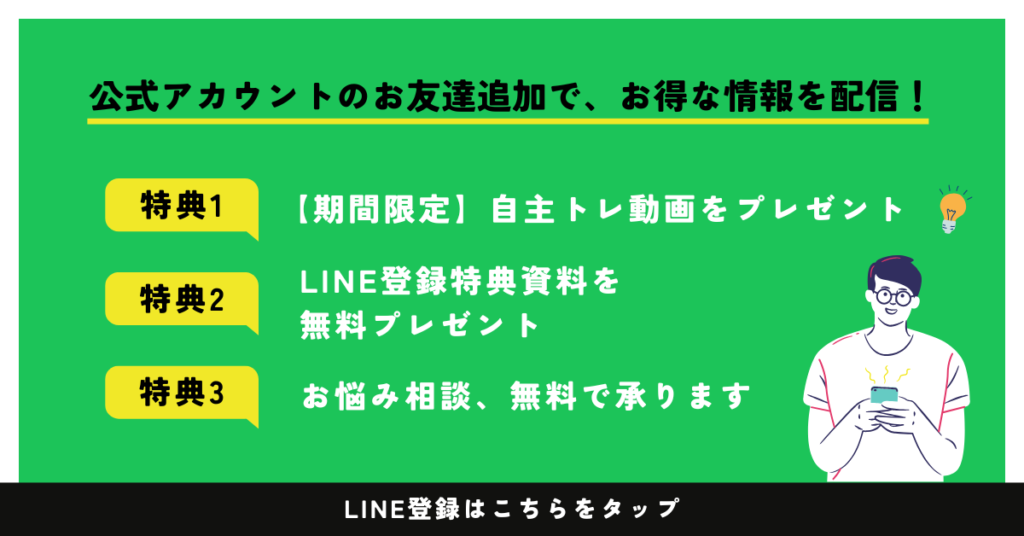
🔥 骨は折れないほうがいいに決まってる
〜片麻痺でも防げる!脳梗塞後の“骨折リスク”をゼロに近づけるマヒリハ式メソッド〜
こんにちは🌞
脳梗塞リハビリ専門施設マヒリハの原田です!
脳梗塞後のリハビリで、私たちが“絶対に避けたい”出来事があります。
それが 骨折 です。
リハビリの途中で転倒 → 骨折してしまうと…
-
痛みで動けない
-
ギプスやコルセットで固定
-
リハビリ中断
-
筋力低下・関節拘縮
-
回復が大幅に遅れる
-
生活レベルが落ちる
-
再び転倒しやすい体に…
という、まさに 負のループ に一気に落ちてしまいます。
今回は、脳梗塞リハビリのプロとして、
片麻痺の方が “なぜ骨折しやすいのか” を根本から説明し、
今日からできる 具体的で現実的な骨折予防策 をお伝えします。
あなたの「動ける未来」を守るための、大切な知識です。
🧭 まず結論(忙しい人向け)
-
片麻痺の方は健康な人より 転倒しやすい+骨が弱くなりやすい
-
その2つが重なるため、骨折リスクは大幅に上昇する
-
特に危険:大腿骨頸部骨折/脊椎圧迫骨折
-
防ぐ方法はシンプル
👉 ①転ばない環境
👉 ②骨を強くする生活習慣
👉 ③麻痺側に体重を乗せる正しいリハビリ -
専門家のサポートを受けながら進めればリスクは大きく減らせる
結論:
“転ばない体 × 折れない骨” を作ることが脳梗塞後の最優先課題です。

❓ なぜ脳梗塞後は骨折しやすいのか?(専門家が見る3つの核心)
① 転倒リスクが一気に上がる
脳梗塞後の身体では、以下のような後遺症が複雑に混ざり合っています。
-
バランス能力の低下
-
麻痺側への荷重量低下
-
足裏の感覚鈍麻
-
空間認識のズレ
-
注意が分散しやすい(デュアルタスクが苦手)
つまり…
「何もないところでも転びやすい体」になっている
ということです。
② 麻痺側の骨がスカスカになる(廃用性骨萎縮)
骨は “負荷がかかる” と強くなります。
しかし、片麻痺では…
-
麻痺側に体重を乗せにくい
-
歩く量が減る
-
関節にかかる刺激が減る
その結果、麻痺側の骨はどんどん弱くなり、
骨密度が急低下 → 折れやすい状態 に。
③ 骨折後の回復が遅い
骨折後は固定が必要になります。
麻痺がある方にとっては、
固定=使わない期間が長くなり、
-
筋力低下
-
関節拘縮
-
歩行再獲得に時間がかかる
-
活動性が低下 → 再転倒リスク増大
という“二次的な悪化”が起きやすいのです。
だからこそ骨折は絶対に避けたい。
これが私たちマヒリハが常に骨折予防を最優先にしている理由です。

⚠️ 特に危険な骨折(脳梗塞後に多い2大骨折)
① 大腿骨頸部骨折(足の付け根)
転倒で最も多い・最も危険。
-
手術が必要になることが多い
-
長期入院
-
歩行能力が一段階落ちることも
-
最悪寝たきりの入口に
歩行レベルに大きく影響するため、絶対に避けたい骨折No.1。
② 脊椎圧迫骨折(背骨)
尻もち、椅子にドスンと座る、くしゃみ、荷物を持つ…
日常の些細な動作で起こります。
こんな症状があれば要注意👇
-
背中や腰の突然の激痛
-
座る・立つ・寝返りで痛む
-
背中が丸くなってきた
放置すると慢性痛や姿勢悪化につながるため注意が必要です。
⏳ 骨折したらどれくらいで治る?(現実的な目安)
骨がくっつくまでの一般的な期間:
-
肋骨:3週
-
鎖骨:4週
-
前腕:5〜7週
-
脛骨:8週
-
大腿骨(足の付け根):12週以上
ただし、麻痺がある場合は…
👉 本当の回復には数ヶ月〜半年以上かかることが多い
👉 元の歩行レベルに戻らないケースもある
だからこそ、そもそも 折れないようにすることが最重要。

🔰 今日からできる“骨折予防”マヒリハ式3ステップ
① 転倒しない環境作り(効果は最速)
-
手すり設置(廊下・トイレ・浴室・玄関)
-
夜間ライトで足元を照らす
-
つまずく物(敷居・コード・ラグ)を排除
-
滑りにくい室内履き
環境を変えるだけで事故の8割は防げます。
② 骨を強くする生活(毎日の積み重ね)
-
カルシウム:牛乳、豆腐、小魚
-
ビタミンD:鮭、きのこ、日光浴10–15分
-
ビタミンK:納豆、緑黄色野菜
+
適度な荷重刺激(=正しく立つ・歩く) が最も重要。
③ 麻痺側に“適切に”体重を乗せるリハビリ
脳梗塞後の骨密度維持には、
👉 ただ歩くのではなく
👉 麻痺側にしっかり荷重する ことが決定的に重要。
専門家がサポートすることで安全に実践できます。
-
平行棒での荷重練習
-
立位での左右荷重比の調整
-
麻痺側下肢の筋トレ
-
歩行介助+装具調整
-
バランス訓練
これらは全部、転倒予防と骨折予防に直結します。
🏁 まとめ:骨折は「予防できる」最大級のリスク
-
脳梗塞後は転倒しやすくなる
-
麻痺側の骨は弱くなる
-
骨折すると回復は長期化
-
しかし、正しい環境+食事+リハビリで大幅に防げる
もし、
「転ぶのが怖くて、動くのが不安…」
そう思っているなら大丈夫。
マヒリハでは、
“転ばない体 × 折れない骨” を実現するプログラムを
その人の状態に合わせて設計しています。
一人で悩む必要はありません。
一緒に、安心して動ける生活を取り戻しましょう。
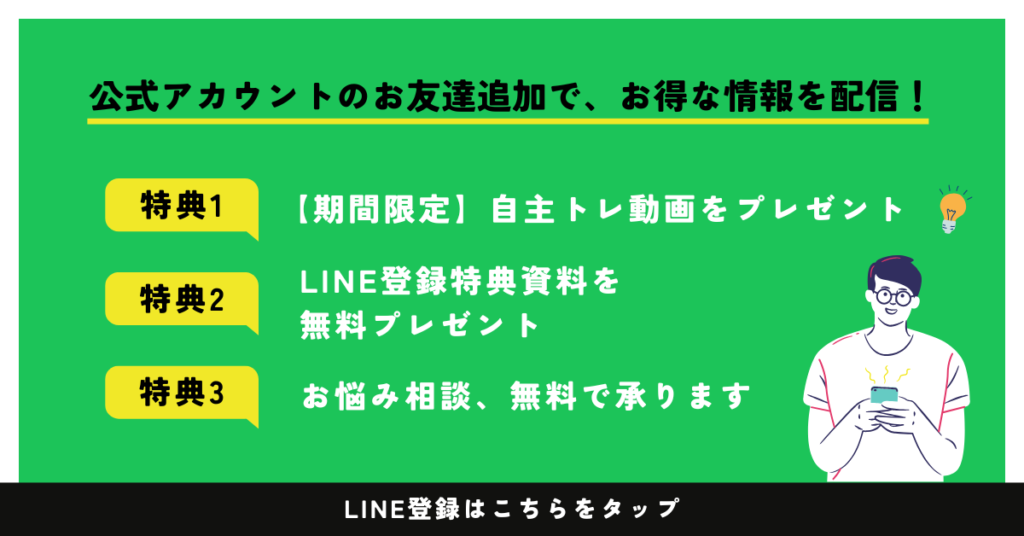
ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ
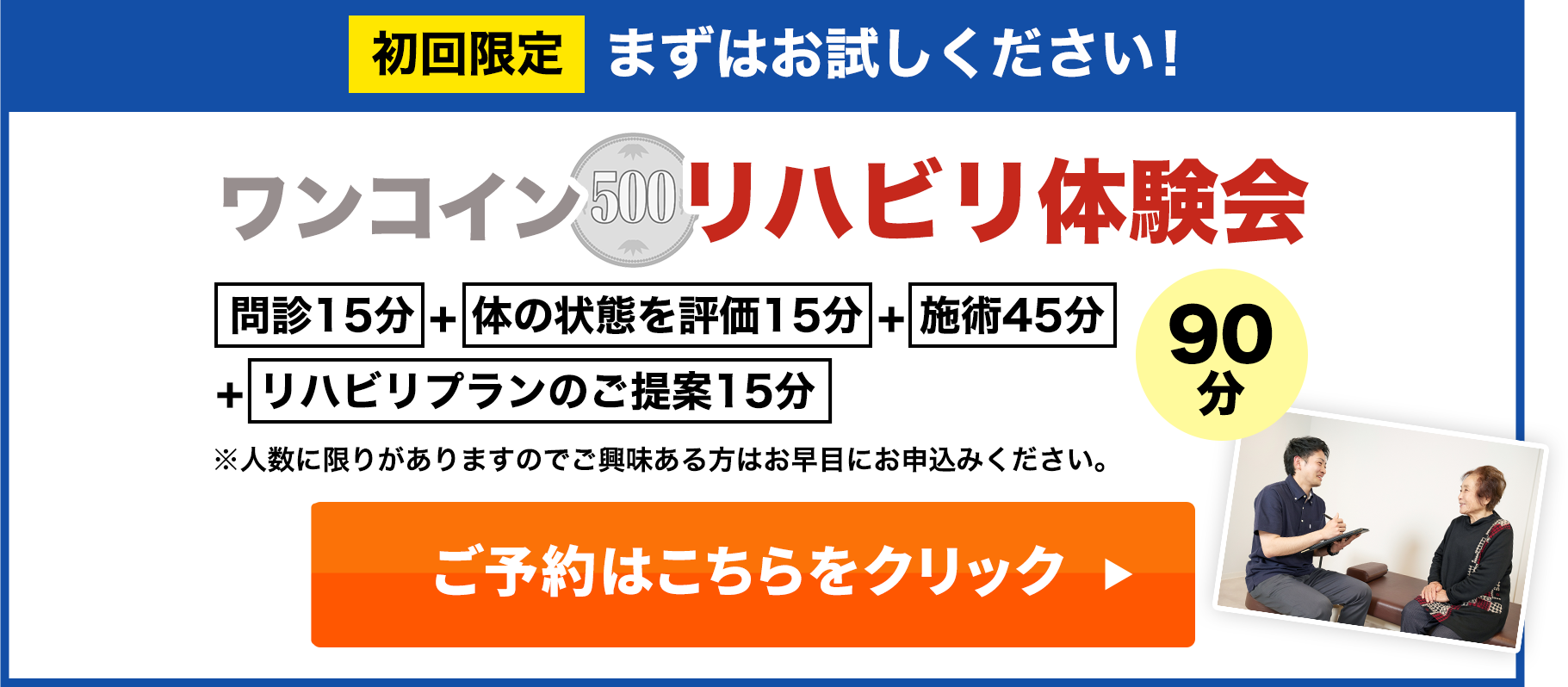
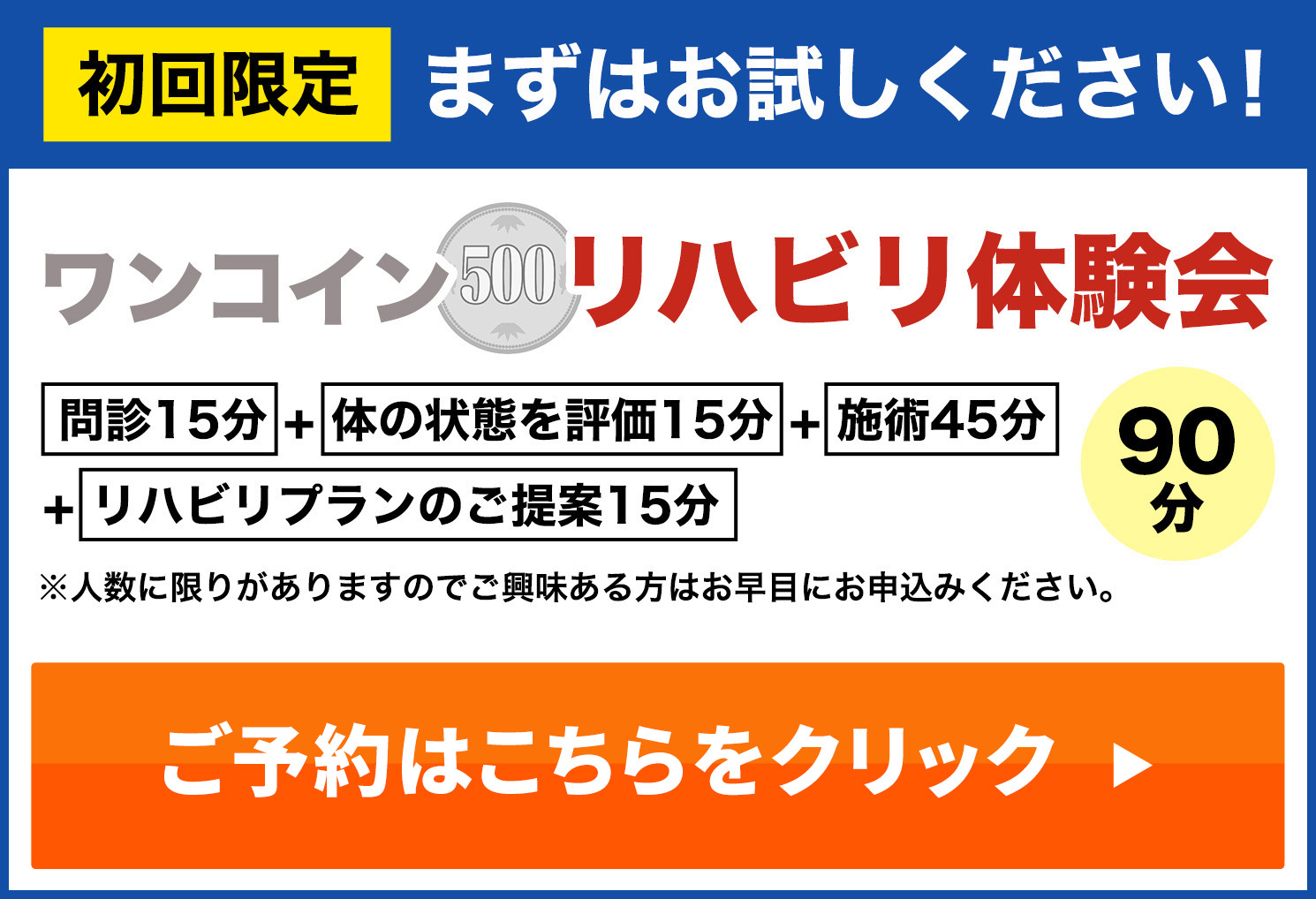
| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |
|---|---|
| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |
| 電話番号 | 04-7197-5090 |
| 定休日 | 日、金、祝 |