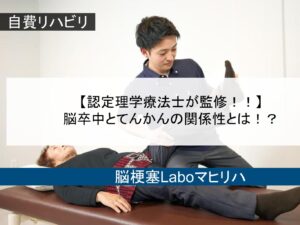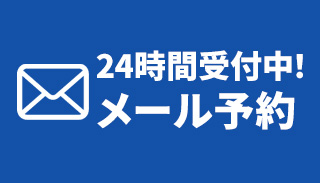【認定理学療法士が監修!】脳卒中後に「覚えられない」のはなぜ?記憶障害の症状と家族ができる4つの対処法
ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)
脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。
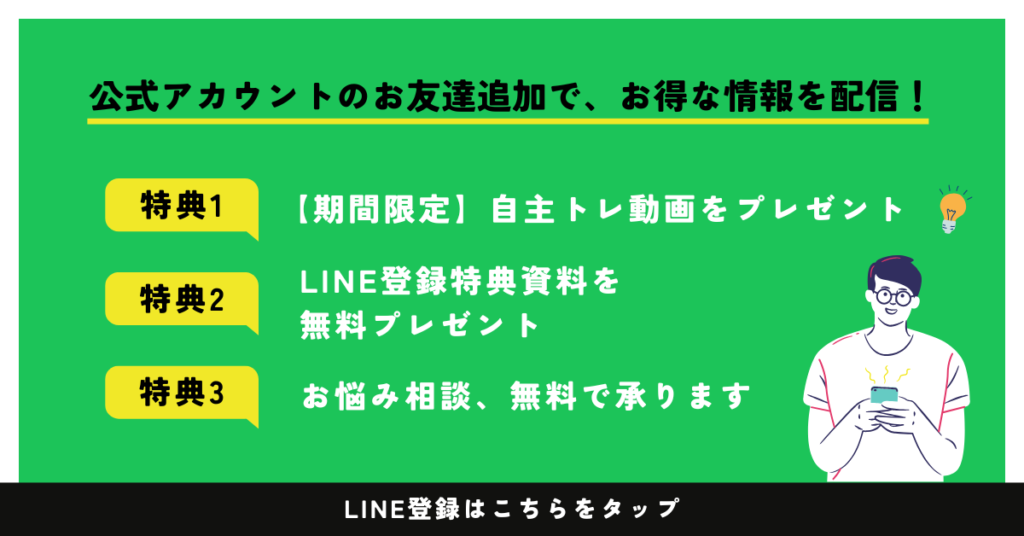
こんにちは! 脳梗塞リハビリ専門施設「マヒリハ」の原田です🌞
「さっき言ったことを、もう忘れている」 「同じことを何度も聞いてくる」 「新しい予定や、人の名前が全く覚えられない」
脳梗塞や脳出血を発症された後、ご家族がこのように感じ、戸惑うことは少なくありません。 身体の麻痺と同時に起こりやすい、これらの「目に見えない後遺症」が、**高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)**です。
その中でも、特に発症する確率が高く、日常生活に大きな影響を及ぼすのが**「記憶障害」**です。 外見からは分からないため、「やる気がない」「ふざけている」と誤解されやすく、ご本人もご家族も深く悩んでしまうケースが多くあります。
今回は、この「記憶障害」に焦点を当て、その種類と、ご家族や職場の方にも今日から実践していただける具体的な対処法について、専門家の視点から詳しく解説します。
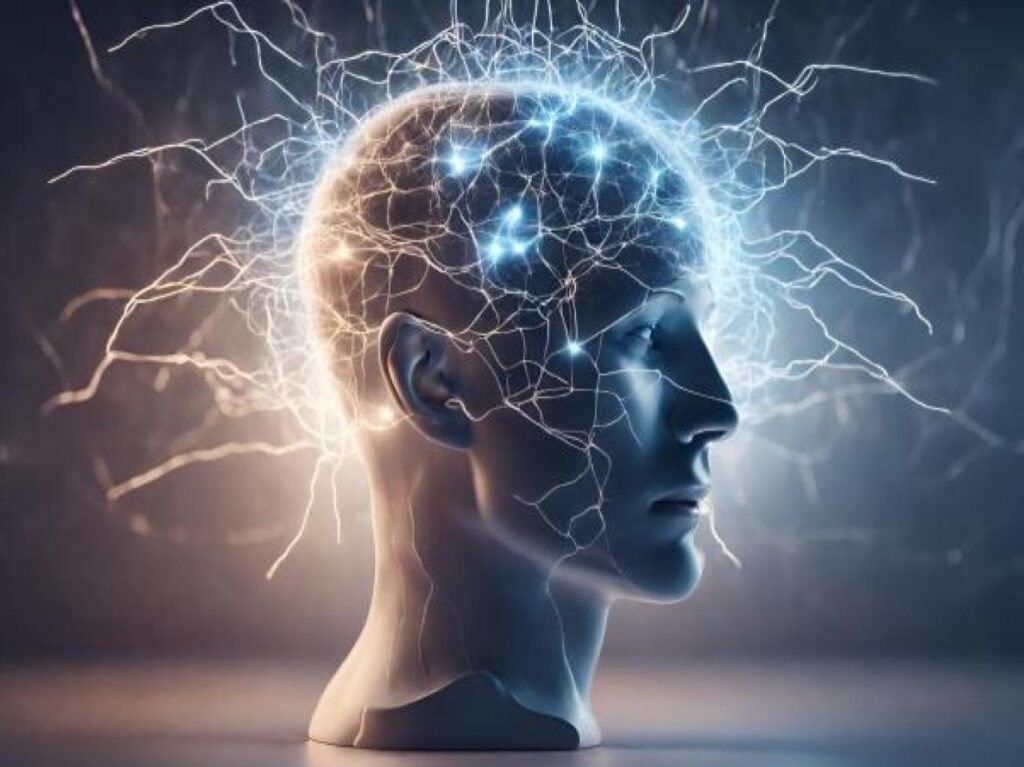
「記憶障害」とは?高次脳機能障害の一つ
まず、高次脳機能障害とは何かを簡単に説明します。 公益社団法人 東京都医師会は、以下のように定義しています。
高次脳機能障害とは、病気や事故などのさまざまな原因で脳が部分的に損傷されたために、言語・思考・記憶・行為・学習・注意などの知的な機能に障害が起こった状態を指す。 (公益社団法人 東京都医師会 「高次脳機能障害について」引用)
具体的には、
- 注意力や集中力が続かない(注意障害)
- 言葉がうまく出てこない(失語症)
- 感情のコントロールが効かなくなる(社会的行動障害)
などが挙げられます。 そして、 その中でも特に多い症状が、「新しいことが覚えられない」といった記憶障害なのです。
あなたの「忘れっぽさ」はどのタイプ?記憶障害の5つの分類
「記憶障害」と一口に言っても、その現れ方は人によって様々です。どの記憶が苦手なのかによって、対処法も変わってきます。
1. 短期記憶障害 数分から数時間といった、ごく最近の新しい情報を記憶しておく機能の障害です。
- 例: 昨日の夕食を思い出せない。さっき話した内容を忘れてしまう。
2. 長期記憶障害 数日から数年、あるいはそれ以前の古い記憶を思い出す機能の障害です。
- 例: 子供時代の思い出や、以前住んでいた場所が分からなくなる。
3. エピソード記憶障害 ご自身が体験した出来事(エピソード)を思い出せない障害です。「いつ・どこで・誰と・何をした」という体験そのものの記憶が抜け落ちます。
- 例: 旅行に行ったことは覚えているが、何をしたか思い出せない。「さっき薬、飲んだっけ?」
4. 意味記憶障害 言葉の意味や、一般的な知識(常識)が分からなくなる障害です。
- 例: 「1年は365日」「このペンは紙に書くもの」といった知識が抜け落ちる。「あれ」「それ」などの指示語が多くなる。
5. 手続き記憶障害 自転車の乗り方や箸の使い方など、繰り返し行うことで「体が覚えている」動作の手順を忘れてしまう障害です。
- 例: ピアノの弾き方、ネクタイの結び方が分からなくなる。
記憶障害のリハビリ:「鍛える」のではなく「補う」という発想
ご家族から「どうすれば記憶力が鍛えられますか?」とよくご質問を受けます。 結論から言うと、筋肉のように記憶機能そのものを「鍛えて治す」ことは非常に難しいとされています。
そのため、記憶障害のリハビリは、記憶力を取り戻すことではなく、**「記憶できなくても日常生活や社会生活に適応できる方法を身につける」**ことを目標にします。 ただし、 適切に指導・訓練することで、ご本人に合った「新しい工夫の方法」を学習し、生活に活かしていくことは十分に可能です。
専門家が実践!今日からできる4つの対処法
リハビリの現場では、ご本人の状態に合わせて、主に4つのアプローチを組み合わせて行います。これはご家庭や職場でも応用できる考え方です。
1. 環境調整(家族ができる最大のサポート)
ご本人の「記憶力」に頼るのではなく、「記憶しなくても済む」ように周囲の環境を整える、最も重要で効果的な方法です。
- 物理的環境: 物の置き場所を固定し、中身が分かるように写真やラベルを貼る。(例:棚に「靴下」「下着」と貼る)
- 生活全般: 一日のスケジュールを決め、可能な限り変更せず、規則正しい生活(ルーティン)を送る。
- コミュニケーション:
- 話しかける時は、まず名前を呼んで注意を向ける。
- 一度にたくさんのことを伝えず、「一つずつ」具体的に指示する。
- 重要な予定や約束事は、必ず紙に書いて目につく場所(カレンダー、冷蔵庫など)に貼る。
2. 学習法の工夫(エラーレス学習)
新しい作業手順などを覚える際は、**「エラーレス学習(間違えさせない学習)」**が非常に効果的です。 なぜなら、エピソード記憶が障害されていると、間違えたことを修正しても「修正した体験」自体を忘れてしまい、同じ失敗を繰り返してしまうからです。 (失敗体験が手続き記憶として記憶され、反射的に失敗するようになることさえあります)
最初から正解を教え、成功体験を積んでもらうことが、結果的に正しい方法を身につける近道になります。
3. 代償手段の活用(メモとアラームは必須アイテム)
ご本人の頭で覚えるのではなく、「道具」に記憶を代行してもらう訓練です。
- 外的補助手段(推奨): 最も一般的で効果的な方法です。忘れることを前提に、メモ帳、日記、カレンダー、スマホのアラーム、ICレコーダーなどを使いこなす練習をします。最初は抵抗があっても、使いこなせるとご本人の自信に繋がります。
- 内的補助手段: 「桜木さん→桜の木」のように、頭の中でイメージを関連付けて覚える方法などですが、ご本人の負担が大きく、難易度が高い場合があります。
4. グループ練習(「自分だけじゃない」という安心感)
記憶障害を持つ方は、度重なる失敗体験から自信を失い、社会的に孤立してしまうケースが少なくありません。 同じ悩みを持つ仲間と集うグループ練習は、不安やストレスを和らげる効果があります。また、他の人が実践している工夫(代償手段の使い方など)を学ぶ、貴重な情報交換の場にもなります。
【まとめ】
脳卒中後の記憶障害は、目に見えないからこそ、ご本人も周囲もつらい思いをしがちです。
「記憶障害かも?」と思ったら、まずは専門家(医師、言語聴覚士、作業療法士など)に評価してもらうことが第一歩です。 そして、どのタイプの記憶障害なのかを評価してもらった上で、ご本人、ご家族、職場が「忘れるのは病気のせいだ」という共通の理解を持ち、生活しやすい環境(代償手段や環境調整)を一緒に整えていくことが、ご本人の安心と社会復帰に繋がります。マヒリハでは、このような高次脳機能障害に対しても、専門的な評価とリハビリを行っています。一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。
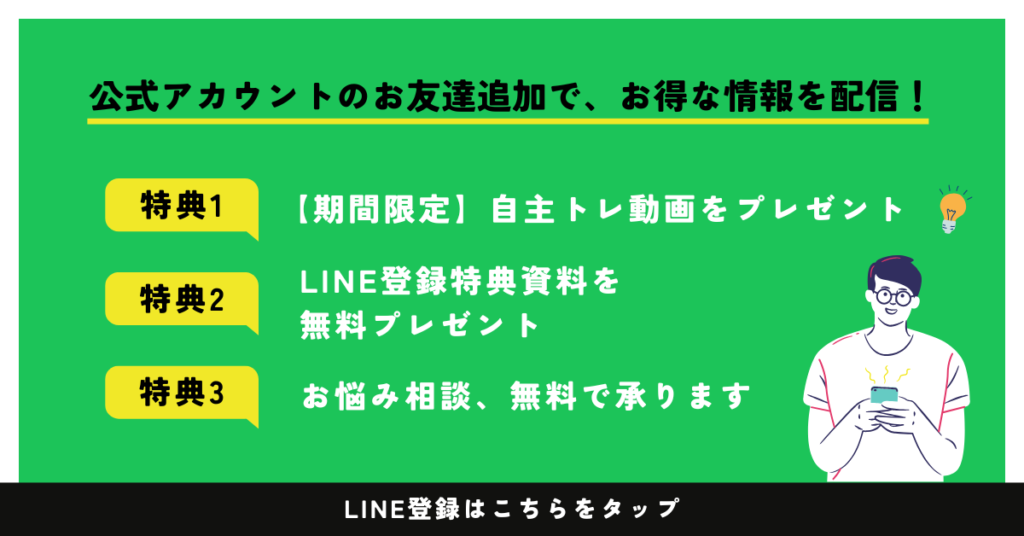
ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ
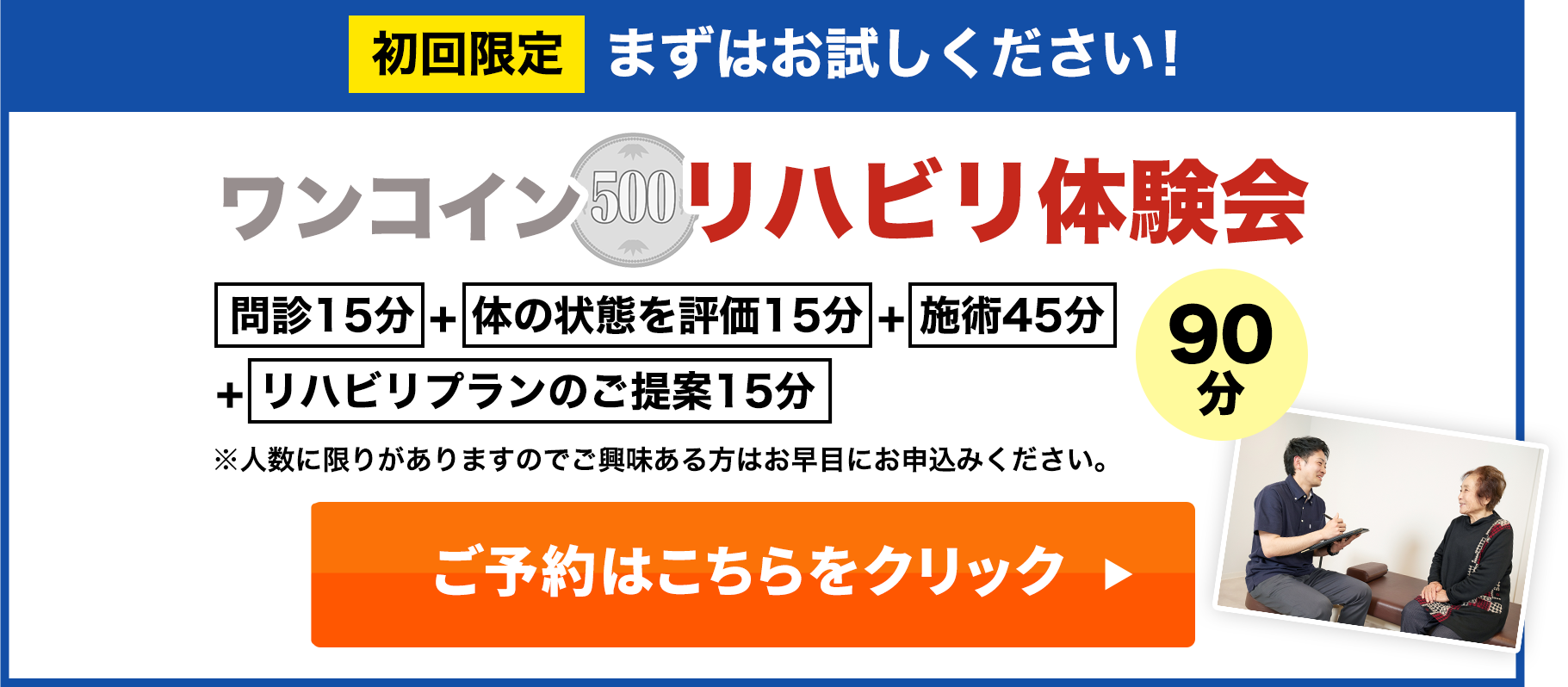
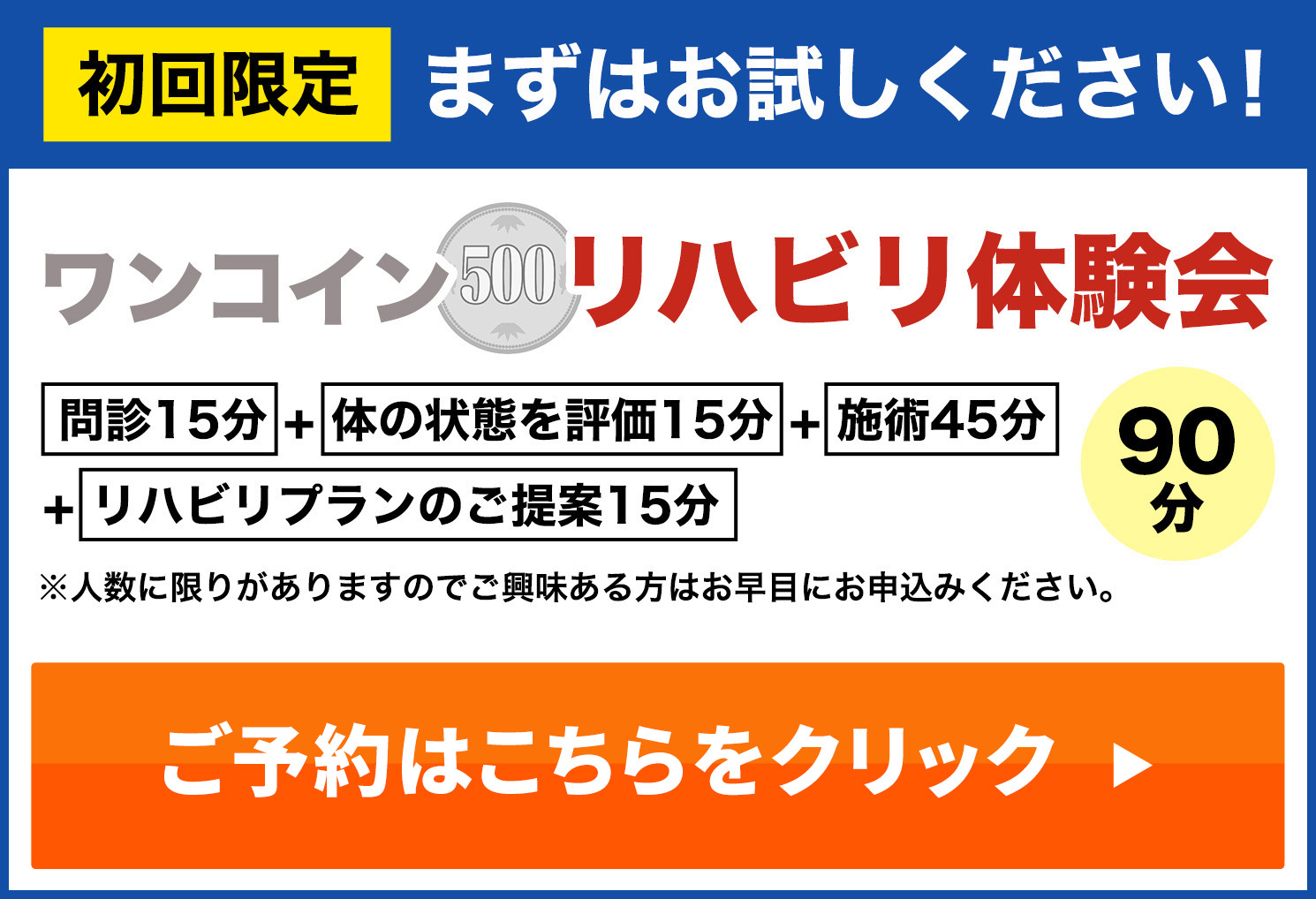
| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |
|---|---|
| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |
| 電話番号 | 04-7197-5090 |
| 定休日 | 日、金、祝 |